
未知なる頂へヒマラヤ17・・・17日間の短期速攻記録
記録:坂原忠清
最後の氷壁が
降雪の中でゆらめく
激しい息づかいが
静寂の中で
一つの孤独な生命の存在を告げる
1979年8月15日午後4時31分
未知なる頂
ビンドゥゴルゾムⅡ峰に登頂
天気 雪

| Contents | |||
| ヒマラヤ登山記録 | チベット | 1998~2006年 | |
| 《A》 | ヨーロッパ・アルプス(アイガー、マッターホルン、モンブラン) | スイス、フランス | 1975年7月~8月 |
| 《B》 | コーイダラーツ初登頂(5578m) | アフガニスタン | 1977年7月~8月 |
| 《C》 | ムスターグアタ北峰初登頂 (7427m) | 中国 | 1981年7月~8月 |
| 《D》 | 未知なる頂へ (6216m) ビンドゥゴルゾム峰 | パキスタン | 1979年7月~8月 |
| 《E》 | ヌン峰西稜登頂 (7135m) | インド | 1985年7月~8月 |
| 《F》 | ナンガ・パルバット銀鞍 (8126m) | パキスタン | 1983年7月~8月 |
| 《F2》 | ナンガ・パルバット銀鞍 (8126m) その2 | パキスタン | 1983年7月~8月 |
| 《G》 | ナンガ・パルバット西壁87 (8126m) | パキスタン | 1987年7月~8月 |
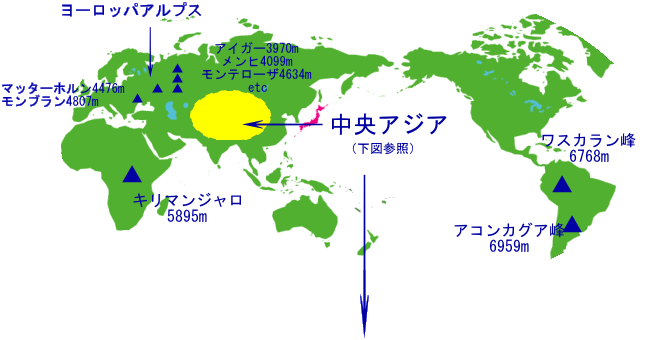
中央アジア遠征峰
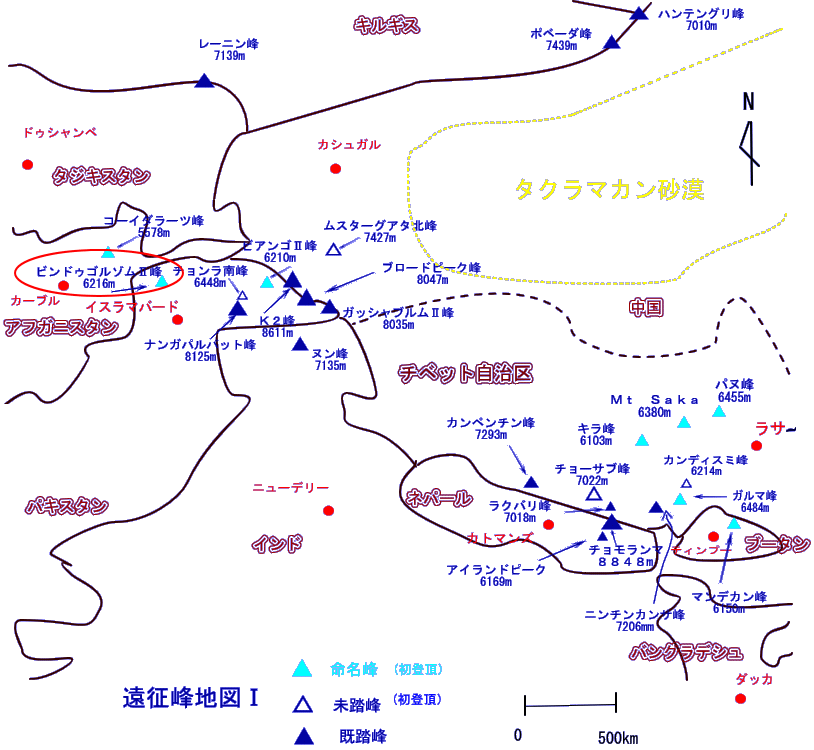 |
![]()
 |
Page1 |
|---|
|
ヒマラヤ17 ビンドゥゴルゾムⅡ峰、この山に近づいた者はいない。山裾をえぐる急峻な二つの氷河はいずれも登攀困難な幾つかの氷瀑帯を連ねアプローチを閉ざす。1938年英国隊、49年、50年ノルウェー隊、64年アメリカ隊・・・etc。 |
低いながらもヒマラヤの困難な未踏峰を17日間で落とそうという無謀な計画「ヒマラヤ17」は絶望だけを予感させつつ紅蓮となって私の胸に宿った。際限もなく不可能に近い困難を前にして、追いつめられた動物が極度の緊張に全神経を燃焼させる瞬間の不条理なエクスタシーを私は久々に味わった。 安住が「死せる生」であることを知りながら、より高次元での安住を求め内なる荒野へ第一歩を踏み出した知的存在は、多くの犠牲を払い不毛の地に未来を語り継いだ。未来とは安住を求め安住を拒否し続ける生の自己運動によってもたらされる壮大な生命の軌跡であり緲々たる時空の彼方への終わりなき飛翔である。 |
私には自分の選んだ苦痛が理解できなかった。一刻も早く安住の地へ逃げ帰りたかった。しかし私は確かに選んでしまったのだ。鋭い寒気と寂寥が、私のカオスの上に形成されつつある内なる荒野を鮮やかに映し出した。それはもう一つの世界とのスビダーニア(めぐり会い)であり、新たなる私のテリトリーであった。 アルプスをさすらい樹木や岩や氷雪の声を聴き、オクサスの未踏峰に立ち、沖積土のもたらす豊饒と氾濫の描くゆるやかな生命の波紋の広がりを見つめ、テリトリーの地平線上にかすむ困難な山、ビンドゥゴルゾムを私は追い続けた。 |
 |
Page2 |
|---|
|
1章 未知なる頂へ 雨がテントをたたき、憂鬱なリズムを醸しだす。今日も又雨だ。朝の交信タイムには、まだ早い5時であることを確認して、再びまどろむ。6時17分の定時交信を寝過ごし、7時17分、今日初めての連絡をベースキャンプと行う。 雨の中で昨日キャンプ1への最終荷揚げが行われ、300㎏の登攀具。食料、ガス等が荷揚げされたが、岩野は身体の調子悪いとのことで荷揚げを行わず、ベースキャンプに止まる。現在キャンプ1には4名が集結 |
し第二アイスフォール突破を目指し、意欲を燃やしている。ところが雨は相変わらず降り続き氷河の崩壊を早め、岩なだれを誘い我々の前進を拒む。 |
にしたい」とのこと。この雨じゃ誰だって危険な氷河に身をさらしたくない。キャンプ1でもさしあたり停滞と決める。 |
 |
Page3 |
|---|
|
調子に乗って岩なだれがコーラスし、雨音がやかましく騒ぎたてる。 午後になって、5日ぶりの青空を「チラッ」と見た。我々のスケジュール「ヒマラヤ17計画」に停滞日はない。行動あるのみ。 |
両手に構え、おもいきりジャンプする。「ガリリ」とアイゼンとピッケルが氷を食む。- 止まった! 成功 -次は大きなクレパスだ。亀裂のせばまっている地点までトラバースして観察すると、そこはスノーブリッジの壊れた跡であった。 |
アイゼンをはいたまま背中に乗られると聞いて、博夫は一瞬、痛みを感じたようである。安心しろ。背中に穴はあけはせん。背中に乗って、おもいきり身体をのばし、ピッケルをクレパスの縁に打ち込む。確かな手応えが返ってくる。 |
 |
Page4 |
|---|
|
セーターは我慢できるが、何としても靴だけは濡らしたくない。一度濡らしたら、ベースキャンプに下らない限り、乾かすことはできない。またキャンプを進めるにしたがって、どんどん高度も上がるので濡れた靴では、凍傷にかかり易くなる。だがそんなことにはおかまいなく無情にもヘルメットの雫は靴の上に「ポタリ、ポタリ」 |
ここから上は、しばらく凹凸の少ない氷河が続く。小さい氷の亀裂が、かなりたくさん走っている。ヒドンクレパスに注意しながら一つ一つ飛び越える。 今超えた大クレパスを見下ろすとすさまじい景観である。 |
今日は大分濡れたが、第二アイスフォールの本格的な攻撃を始めることが出来たので、明るい気持ちでキャンプ1にもどる。闇に包まれた氷河の上に星々が煌き出す。明日は晴れるかも知れない。 (2)雪霧の中の絶望 |
 |
Page5 |
|---|
|
ルートはアイスビルディングの直登以外に無さそうである。しかし、この氷壁は、ほとんど垂直にそそり立っている。5m程ダブルアックスで登るが、身体が空中に出てしまい、バランスがとれない。
|
やがて氷壁の上部へ姿を消し、ザイルの動きが止まる。 |
まず、氷塊が互いにぶつかり合ってできた氷のトンネルにもぐり込む。4m程進んだ途端に、突然クレパスに落ちる。新雪がたっぷり詰まっていて、もがけど身体が上がらない。 |
 |
Page6 |
|---|
|
際限もなく降り続ける雨の中で、私はクレパスを凝視したまま、しばし立ちすくんだ。気が付くと顔から雫がたれていた。手袋も靴も、かなり濡れている。
|
「ごくろう」 |
テントの中にザイル、ハーケン、ガスバーナ等を収納し、2時、城砦を後にした。この次、このテントと再び会うことがあるだろうか? |
 |
Page7 |
|---|
|
特に氷の崩壊と雪崩の起こる場所、頻度、規模について、注意深く調べたが、ひっきりなしに起こる雪崩は、キャンプ1に3本流れ込んでいる氷河の1つ、中央氷河にほとんど集中しており、右氷河のアイスフォールは静かである。 時折、右岸のアイスフォールが崩れ落ちるか、又は左岸西壁のガリーから、雪崩やものすごい落石がある程度である。どうやら第二アイスフォール中央部の雪崩の頻度は周囲に比較すると少ないようだ。 多分、城砦左側の雪崩道も、雪崩の定期便の通り道であって、周期も2,3日に1度ぐらいなのであろう。上部氷河の巨大なアイスビルディングが崩壊すると、この雪崩道に出口を求めて、氷塊が殺到し雪崩道が甦えると考えられる。 |
重い荷、高度での激しい行動、希望のない天気。先の見えない疲労の中で、ただひたすら眠りこくっている。
|
1時30分、仮のキャンプ2城砦下部着。遅れている林田、日下部を待つ。キャンプ1で作ってきたリンゴジュースを飲む。 「うまい」 ポリタンから口を離すのがつらい。いくらでも飲める。実際、身体は水分と糖分を要求している。 ―もっと飲みたい― 2時、赤旗マークを付けた竹竿だけを持った空身の私がトップに立ち、ザイル、スノーバー、をザックに詰めた博夫を従え、荷上げ隊より一足先に、城壁下部を出発する。昨日、キャンプ1で観察した雪崩道に向かって、城砦下部を左へトラバースする。
|
 |
Page8 |
|---|
|
「ルート開拓の可能性を見出すことが出来ない場合、我々は同ルートをもどる。出発して30分たって、もどるという我々のコールが無かったら、ルート工作は成功していると判断して、仮キャンプ2の荷を持って、我々のルートを追ってきて欲しい」と伝えて、荷上げ隊の2人と別れてきたがふと不安がよぎる。 ―荷上げを焦りすぎたか― やはり我々ルート偵察隊がルートを確かめてから「O.K」のサインをだすべきであった。今からもどって、そのことを2人に伝えるべきか? 思惑から醒めると、私は雪崩道の急な氷の斜面で、立往生していた。右手にマークのついた竹竿を持っているためアイスバイルが使えない。アイゼンを強くけりこんでも、氷が硬くて、爪はわずかしか食い込まない。しかたないので、不安定な姿勢のまま右手をおもいきりふるいピッケルでステップを切る。 1歩1歩、ステップの跡を辿り、博夫が近づく。ほんのわずかスリップすれば、雪崩道を博夫は、矢のように落下するであろう。ザイルがいっぱい延びきったところで、次に私の落下が始まる。 堅い氷の滑り台を、2人はザイルに結ばれたまま場外下部へと突進し、やがて氷塊に激突し、砕け散るだろう。 |
雷鳴と風の唸る富士に、ためらいを感じつつ、3度目の高所順応テストのため、博夫と2人で山頂に向かった。予想通り、9合目で猛吹雪に襲われた。
雪が弾丸のように突き刺さり、進むどころか、立っている事さえ困難な吹雪であった。ビバークを決意し、テントを取り出している最中に、強風で次々とポールが折れ、いたしかたなく、テントを突破ぶって氷の上で横になった。 やけに寒くて、身体が脹らんで重い。アタックコートのチャックを開くと、びっくり。内側に大量の雪が詰まっている。あまりにもすごい強風が、コートの繊維のわずかな隙間を突き抜け雪を運んだのであろう。オーバーズボンの中もたっぷり雪が詰まっている。 寒いはずである。面白い程、震えが止まらなかった。2人で「ガタガタ」音をたててふるえた。 翌朝快晴、山頂の気象台で、私を知っているという職員に会い、コーヒーとトーストをごちそうになり、ビバークの後の豊かな、満ち足りた気持ちで山頂を後にした。 「谷川岳衝立岩正面壁に続いてのビバークだったな。次のビバークは、たぶんヒマラヤだろう。死ぬかも知れんぞ」 寡黙で、気取ったことを言わない博夫がさらりと言ってのけた。博夫は、私の宿命的感覚を超えて、充分に逞しいのである。 雪崩道は、アイスビルディングを削り取りながら城壁上部へと続いていた。予想していた通りであったが、目の前に展開された世界は、まるでクレバスの展覧会であった。 至るところが「ズタズタ」に裂けていて手の出しようがない。 どだい、アイスホールのど真中を突破しようなんて、無理な話なのだ。しかし日数的に、ルートの変更は不可能である。1度、ベースキャンプまで降りて、ルートの偵察から、やり直すには最低、2週間はかかる。 ―「ヒマラヤ17計画」最早これまでか。 乱立する氷塔と底知れぬ深い口を明けたクレパスの一つ一つを、丹念に目で追う。その一つ一つを突破するのに必要なザイルの長さ、スノーバーの数、ワイヤー梯子の長さ、時間、労力を直感的に読み取る。 「だめだ。とてもじゃないが、これ以上の前進は無理だ」・・・・・・・もう一度、極悪な相を呈し、拒絶する氷の津波群に目を向ける。キャンプ1で、しっかりと瞳に焼き付けた第二氷瀑帯を思い起こす。 ― 城壁上部はどうなっていたか ― |
何とか明るいうちに迷路を抜けよう。『博夫、やはり次のビバークは、ヒマラヤになりそうだ』
無言の語りかけをしてみる。
氷の迷路は、全体がクレバスの巨大な空洞の上に浮かんでいるのをしめすかのような、不気味な深い穴と亀裂が、至る処に走っている。一歩踏み出すと同時に、迷路そのものが轟音と共に奈落の底へ落ちてゆく不安に襲われる。 又、もし1本でもマークが倒れると我々は引き返すことさえ出来なくなってしまう恐れがある。3本目のマークを氷塊に突き刺した時、再び前進不能になる。このまま更に右へトラーバースを続けるためには、剃刀の刃のように研ぎすまされた氷稜に、ルートを求める以外にない。ひどく尖っていて足を置く場所なんて、ありゃしない。 氷そのものも極く薄いもので、体重を支えてくれるかどうか危うい。この氷板が崩壊すると我々は間違いなくクレパスに落ちる。氷板の右も左も「ぞくっ」とする程、切れ落ちている。 我々はこの氷の刃を「馬の背」と呼んだ。氷からピッケルを抜き、手の届く限り遠くの位置に再度ピッケルを打ち込む。強く引いて見る。 「びく」とも動かない。 安心して、力をピッケルに集中し身体を前方に「じりじり」とずらす。足の裏を内側に向け、両足のアイゼンを氷にひっかけ、木登りするようにして、氷の刃を登る。 冬の前穂北尾根や鹿島槍北壁の雪稜で、良くこんなことをした。アイガー頂上付近の細い雪稜では、落ちないのを不思議に思いつつ、立って「スポスポ」歩いたこともあった。 それ等の思い出と共に、私の内部から不安感が拭い去られ、登攀の喜びが肉体の深奥から「こんこん」と湧き上がってくるのを感じた。今まで恐れを持って、氷の迷路を見つめていた瞳は、一変して大胆な挑戦的な光さえ、宿し始めたような気がしてきた。 |
Index
Next