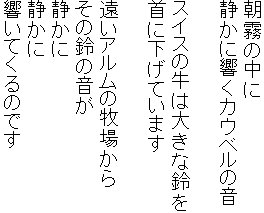 |
欧州アルプス初海外山行・・・ハイジのくにへ
(報告書・《ハイジのくにへ」より抜粋)
記録:坂原忠清
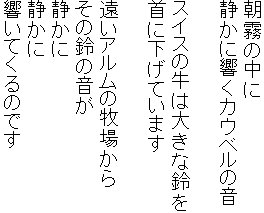 |

| Contents | |||
| ヒマラヤ登山記録 | チベット | 1998~2006年 | |
| 《A》 | ヨーロッパ・アルプス(アイガー、マッターホルン、モンブラン) | スイス、フランス | 1975年7月~8月 |
| 《B》 | コーイダラーツ初登頂(5578m) | アフガニスタン | 1977年7月~8月 |
| 《C》 | ムスターグアタ北峰初登頂 (7427m) | 中国 | 1981年7月~8月 |
| 《D》 | 未知なる頂へ (6216m) ビンドゥゴルゾム峰 | パキスタン | 1979年7月~8月 |
| 《E》 | ヌン峰西稜登頂 (7135m) | インド | 1985年7月~8月 |
| 《F》 | ナンガ・パルバット銀鞍 (8126m) | パキスタン | 1983年7月~8月 |
| 《F2》 | ナンガ・パルバット銀鞍 (8126m) その2 | パキスタン | 1983年7月~8月 |
| 《G》 | ナンガ・パルバット西壁87 (8126m) | パキスタン | 1987年7月~8月 |
![]()
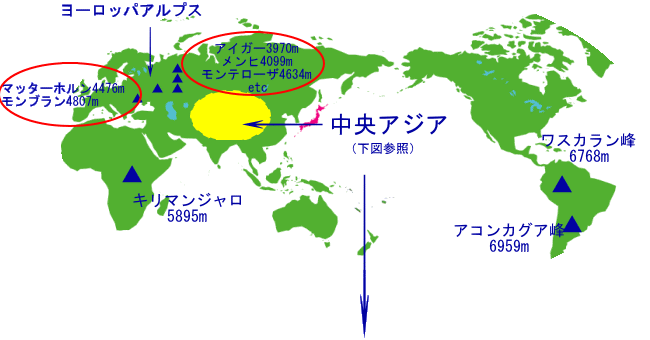
中央アジア遠征峰
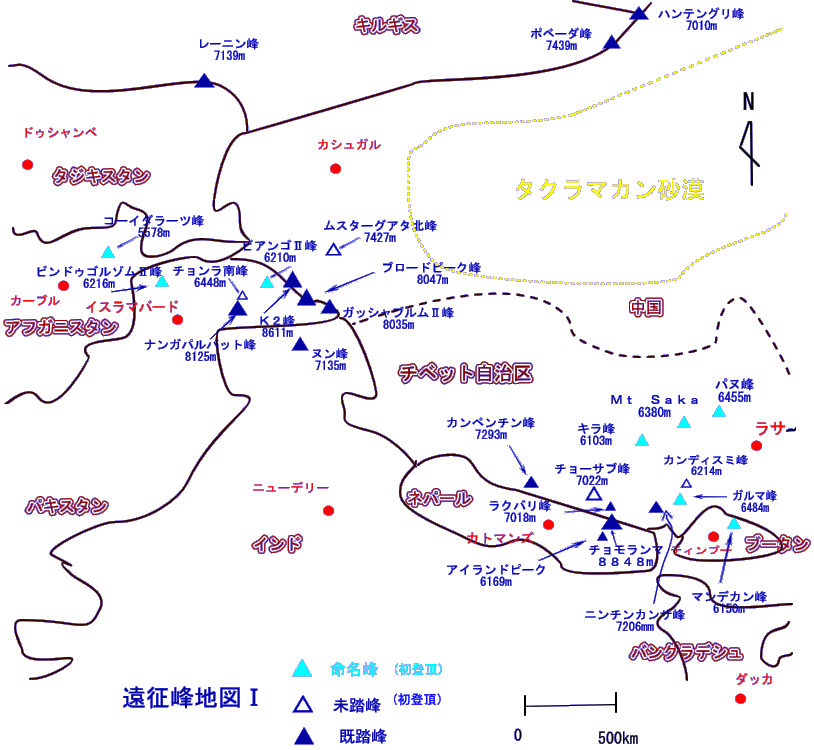 |
 |
Page1 |
|---|
|
アルプへの想い 緑が人間に安らぎを与える理由について考え始めた頃、僕はすでに、かなりたくさんの峰々を歩いていた。奥秩父の深い森の中で、母の胎内に居るような安らかな感動におそわれた時、自らにとっての樹木の意味が明確になった。 |
樹木が自らの生のテリトリーを広げる為、より苛酷な自然条件を求め、一層高い、岩と氷の世界へ出発するように僕も又、旅立った。 生命を拒絶する雪と岩の世界には、母の胎内のような、安らかさはなかった。手ひどく打ちのめされ、しおしおと山を下りる事が度重なる。 しかし、白く冷たいだけの雪や、全ての生命を寄せつけまいとする岩に、樹木としての意識が親しみを感じるには、そう時間はかからなかった。 自然のサイクルの中で、雪も岩も又、確かにプリミティブな母であった。この二度の意識の回帰を経て、僕は「アルプへの想い」にとらわれた。 落ち込んでしまいそうな深い空、瞳が痛くなる程キラキラ輝く白銀の峰々、ゆるやかに蛇行する氷河、氷河のもとに何処までも広がる緑の海アルム、黄色や赤や紫の花が、細波のように風にゆれる。 羊の鈴の音が遠く近く風に乗って流れてくる。アルムに寝ころんで今降りてきた氷河に瞳を凝らす。幾つもの真青なクレパスが目に浮かぶ。更に上方に瞳を移す。 |
とがったホルンの頂きが見える。何時間もかけて登りつめた氷と岩の頂は、その真摯な熱情にやさしく語りかけるだろう。登攀後の満ち足りた疲れの中で暫し微睡む。風の子守歌を聴き、花の香りにつつまれ、太陽の温もりに身をゆだね、僕は自然に還るだろう。 目を醒ますと山々は一面にバラ色に染まる。ペーターが羊を連れて降りてくる。バラ色の光の中に、のどかな羊の声が響きわたる。氷河の冷たい湧き水を一口飲み、僕は羊になって山を下るだろう。 「アルプへの想い」それは根元的に人間でありたいという欲求であるのかも知れない。 |
 |
Page2 |
|---|
|
コペンのねえちゃん グリンデルワルトはドシャ降りの雨だった。電車を降りて駅舎に入る間にぬれてしまう程激しくふっていた。ジュネーブでもたもたしていた為に、もうすっかり外は暗くなっている。
部屋の交渉は成立した。美女はもっとしゃべったのだが、Mr坂に理解できたのはこれだけだったのである。日本語に訳すとこうなる。
|
Mr坂「三人部屋ある?」 美女「ええ、ございます」 Mr坂「一晩いくら?」 美女「105フランです」 Mr坂「風呂と食事ついてる の?」 美女「ええ、何トカカントカ」 Mr坂「チップはどうすんの ?」 美女「結構でございます」 それにしても僕のフランス語が通じるなんて信じられないなーと思ったら、やっぱり信じられなかった。僕のフランス語ではだいたい飯付きのはずなのに、待てど暮らせど飯が来ない。 |
大きな財布を持ってコインをジャラジャラさせながら、レストランの中を縦横無尽に動き回る。出てきたホイテは何の事はない、紐かわ饂飩と肉のごった煮みたいなもんだ。ビールと一緒に流し込んだ。 目の前の窓ガラスの向こうに緑色の登山電車が止まっている。きっとユングフラウの方に行く電車だろう。雨の粒が盛んに電車にあたり、飛び散っている。 レストランを出てロビーに行くと、ビヤダルポルカみたいな、おっさんと、あんまり迫力のないねえちゃんがソファに座っていてジロジロこっちを見る。突然「こんばんは」とねえちゃんが言った。こんな時は何と答えればよいのだ。「グーテンアーベント」か「ボンソワール」か、それともやっぱり「こんばんは」か! |
 |
Page3 |
|---|
| ビヤダルが説明する。「この人、コペンハーゲン大学の日本語の教授だ」へえ~ずいぶん若い教授だな、まだ20代じゃないかな、と思っていると、下のバーに飲みに行こうとさそう。ビヤダルには若い子分が付いていて、どうも彼等は写真家らしいのだ。
薄暗い地下のバーでは、バンドがロックを演奏し、すごい音が渦巻いている。ビヤダルは水を注文し、コペンのねえちゃんはジントニック、Mr春はウイスキー、Mr坂はコニャック、あとはビールだ。 |
「そうだ日本人のあの臆病さと上向け上の官僚主義は何だ」と我々も息まく。 スローテンポの音楽になった。みんな抱き合ってフロアに出て踊り出す。隣に座っているコペンのねえちゃんが踊ろうとさそう。残念ながら生まれてこの方、まだ一度もダンスなんかした事ない。 しかしコペンハーゲンに負けてたまるか日本男児、とは言うもののもう40時間以上も寝てないのだ。抱き合ったらそのままスヤスヤ母の胸に、という事になりかねない。 次にコペンのねえちゃんに会ったのはメンヒ(4099m峰)の雪原であった。ホテルからアルプの牧場に居を移して数日が経った。我々は最初の4000メートル峰登頂に成功し、のんびりした気分で雪原を歩いていた。 ユングフラウヨッホの駅が近づくとハイカーの散歩が目立ち始めた。黄色い長靴をはいたチビクロサンボみたいなコペンのねえちゃんが現れたのはこの時だ。たった数日前の事なのに、何となつかしい事か。 写真家一派は夕日に染まるアイガー(3970m峰)を撮るとか言って、クライネシャィデックに居るので、一人アルプスの雪原に散歩にきたのだそうだ。真夏に雪の上を歩くのが嬉しいらしく、まるで新しい靴を買ってもらったサンボみたいに歩くのだ。雪原の途中にスキー場があった。 我々、日本男児のスキーをコペンのねえちゃんに見せてやろうと勇んで小屋に行ってみたが。小屋のオヤジも滑りに行ってしまっていて、待てど暮らせどもどって来ない。
|
何しろコペンのねえちゃん、スキーなんかまだ一度もやったことがないと言うのだから無理矢理スキーをはかせてしまえばこっちのもの、ダンスのかたきがとれるというもんだ。 そうまでしなくともコペンのねえちゃんの前をスイッスイッと滑れば、溜飲が下がるというものだ。それなのにやっぱりオヤジめ、帰って来ない。何たることだ。あきらめてトボトボとユングフラウの駅へと歩く。駅のレストランで一緒に食事をしビールで乾杯した。 アイガー峰登頂に成功し、テントにもどった日の夕方、又コペンのねえちゃんと飲みたいもんだと思い、アルムの牧場を通り抜けグリンデルワルトに出てホテルへ行ってみた。すでに何処かへ旅立った後であった・・。 「アデュー」とつぶやいてみた。 「アデュー」とは、永遠の別離を意味するフランス語なのだ。 |
 |
Page1 |
|---|
|
アイガー登頂記 アイスメーアの駅からミッテルレギの山小屋まで2時間程なのでボーデンワルトのベースキャンプをゆっくり出発した。天候はどうも安定していないし、これからも良くなりそうもない。労山のパーティに天気図を聞いてみるが、やはり気圧は低いようだ。労山もアイガーをねらっているようだが、動く気配なし。 我々は山小屋での停滞を覚悟して、1週間分近くの食料を荷上げする事にした。直径20㎝もある大きな黒パンやチョコレートを、どっさりザックにつめた。通い慣れたアルムの小道を、のんびりと歩いて駅へ出た。 登山列車は、クライネシャィデックで乗り換えである。アイスメーアの駅までの切符を買おうと、出札口を探すが見つからない。建物はレストランになっていて、駅という感じではない。やっと探して「アイスメーアまで」と言うと、売ってくれない。そう言えば昨日始発駅のグリンデルワルトで求めた時も売ってくれなかった。 |
いったいどういう事になっているのか?再度しつこく「アイスメーアまで三人だ」と繰返すと、紙に何やら書いて切符らしきものを作ってくれた。どうも変である。何故アイスメーアまでと言うと変な顔をしたり、切符がなかったりするのであろうか? そのわけはアイスメーアの駅に降りてみて解った。出口がないのである。アイガー北壁の岩の中にある駅で、外の絶景を見る為に作られた展望駅なのだ。そうとは知らず駅員をつかまえて「ウエルソルテドガール?」(出口は何処?)と何度も聞いた。駅員は答えるのだが、どうも変な方向を示すのである。三度目にやっと真暗な穴蔵が出口らしいと解った。とても歩けるもんじゃない。急いでザックを降ろし、エレキを出す。穴蔵を照らしてみると、ダイナマイトで爆破したままの小さなトンネルが、急角度で下に降りている。 もちろん誰もいない。岩には氷が張り付いている。まるで地獄に下りて行くような厭な気持である。ずんずん下りて行くと穴の右手の方に明りが見えた。出口かと思い近づいてみると、小さな横穴が明りの方へ続いている。横穴を進むには這っていかなければならない。そろり這って行くと、出口は雪にふさがれて、僅かに外が見える程度である。 |
又もとにもどり、トンネルを進むと、再び右に横穴があり、這って行くと今度はどうにか出られそうである。 クレパスの割れ方も、何とも恐ろしく迫ってくる。わずかにミッテルレギの小屋が、雪の頂きの上に見える。雲は今にも全山稜を覆ってしまいそうで、良い気持ちではない。 何処か遠い所で雷が鳴りだした。だが、その雷音は、途切れず加速度的に大きくなってきたのである。遠いどころかすぐ頭上に迫ってきた。「雪崩だ!」 |
 |
Page2 |
|---|
|
気付くと同時、目の前30m程の岩壁をものすごい勢いで雪崩が通過していく。垂直の南壁を1000m以上も落ちてくるのであるから、その勢いたるや、すざまじいものである。 それも目の前でである。あと、5分早く出発していたら、今頃はアーメンである。「すげえな―」の後は深い沈黙のみ。こんな時はさっさとザイルをたたんで帰るべきである。 今までにもよくこんな状況に追い込まれた事があった。進むべきか、後退すべきか。いつだって甘い誘惑は帰れとささやく。「あまりにも無謀だ」、「後退の決意こそ真の勇気だ」、「山は逃げやしないよ」、 |
「お前一人が死ぬのならそれもよいだろうが、あとの二人はどうする」etc。 いつだって帰る為の理由は山程用意されている。それなのに進む為の理由なんて何処を探してもありゃしない。そう思いながらも、目は安全なルートを求めて、岩壁やシュルンドを探る。 |
ザイルはピーンと張ったまま。術無く、一度もどる。呼吸を整えて再度アタック。シュルンドにずぶずぶ落ち込む。だめだ、どうしてもだめだ。抜け出る事さえ出来ない。 こうなると前進する為の方法は唯一。雪崩の真下を通る事だけ、運を天にまかせるしかない。こんな事ばかりやっていると、いつか死んでしまうだろうけど、何しろ今、ここを通過しなければならない。 再度、確保を二人に託し、耳を澄まし、上のシャワーの落ち具合に気を配りながら走り抜けた。とは言っても、急なデブリを乗り越えていくのであるから、歩いているようなもんであったろう。「出た」、ザイルをたぐる。セカンドが走る。通過。ラストが走る。無事通過。 |
 |
Page3 |
|---|
|
小屋は雪稜の上に見え隠れしている。しかし小屋へのルートは、いったい何処にあるのだ。小屋直下の黒々とした岩場か、それとも手前の、急にそそり上っている雪壁か? 後続パーティは我々のラッセルを使ってどんどん迫ってくる。ルンゼの上部でMr.林ルートファインデングを誤り左の岩場に出てつまってしまう。「右の雪壁の方が楽しそうだぜ」とコールしたのだが、その時彼はもう動けない状態らしかった。 後続のドイツ人パーティはコンテニュアスで正面の岩場を乗り越えていく。アイゼンをはいていない。テクニックは確かな感じである。その後を登ってき労山パーティは右の雪壁に出るようである。 |
我々はこのままザイルオーダーを逆にして雪壁にルートをとった。ところがMr.林が下降にもたついている間に労山パーティが登ってくるのでザイルが交差する。その上ジッヘルポイントが得られず、足場は岩の上にうすい雪が付いているという状態で悪い。こんな時、雪崩にやられたらイチコロである。 この雪壁は小屋までダイレクトに突き上げている。再び雪は深くなり慎重にザイルを延ばす。我々とラッセルを交代した労山パーティの足元から雪の塊が一つ転がる。と見る間に表層雪崩になり、我々のすぐ左側をルンゼに向かって音をたて落下していく。ルンゼには後続パーティがいるのだ。ルンゼの中から叫び声が聞こえたが大丈夫だったようである。ほっとする間もなく続けて二度、三度と雪崩が起る。 今まで天気が悪く大分新雪が積もっているところへ気温が上昇したものだから雪崩の条件は、いつものように100%そろっているというわけだ。うまい事に雪崩は我々の直前で左にわずか折れてルンゼに落下する。雪崩の上部を凝視しながら前進する。 |
Mr.春は相当手が冷たいらしく、しきりに手を温めている。彼は北岳で軽い凍傷にやられた事があった。二の舞にならなければ良いが・・・・・。 |
 |
Page4 |
|---|
|
これが槇有恆氏の東山稜初登攀を記念して建てたミッテルレギの小屋なのである。食事はスープとパンであるが、Mr.坂は朝の残り飯で、おむすびをつくってきたので、一人パクつく。 |
フィンステラールホルンは、真っ白に光っている。明暗だけの世界である。雪稜はすぐに終わり、急な岩稜になる。2、3級程度の楽しい岩登りで、グングン高度を稼ぐ。 |
空の碧い深みの中に、無限に続いているような気さえしてくる。しかしそれならそれでよい。あの深い空で泳いでみるのも悪くはないだろう。なんぞと粋がってみる。 |
 |
Page5 |
|---|
|
太いフィックスザイルがあるのでアイゼンを着けずアタックしたが、この3ピッチは一番苦しい登攀であった。フィクスザイルに頼ると腕の疲れが激しくなるので、確保の為にのみ使い、アイスバイルとピッケルで登ったのだが、岩の上の薄い雪とヴェルグラには泣かされた。 |
天と地の境に、辛うじてとどまっている我身が、とてもいとおしく感じられる。パイナップルに舌つづみを打ち、シャッターをきり、8ミリを回し、はるか下方のフィッシャー氷河に向かって子キジを打つ。落ちながら途中で霧になって消えてしまう。 頂きに到る最後のルートは、急峻な細い雪稜であった。雪庇が微妙に張り出し、一歩一歩が緊張の連続であった。頂きはすぐそこにあった。雪の斜面で、雪庇と区別のできぬ不安定な頂きだった。Mr.春は「ドカッ」と倒れたまま動かない。」7月23日午後2時35分であった。誰もいない頂。 西壁を見ると、先行パーティは斜面の端でもたもたザイル操作をしている。見ていても少しも進まない。「きびしいのかなー」。アルプスの頂きは、「日本の山のような憩いの場所には決してなり得ない。 登り以上に苦しい下りがあるし、頂きそのものが雪と氷と風のすみかなのだ。急いで我々も下り始める。すぐに先行パーティに追いつき、コンテでどんどん下る。頂きから、しばらくは雪の斜面、その後急な雪壁が続く。雪壁の途中にルンゼがあり、2回のアップザイレンで下る。 |
ルンゼの下は再び長い雪壁が、うんざりする程続く。少し傾斜のゆるくなった処で、グリセードしてみる。下部が氷でその上に腐った雪がのっているので、雪崩状になる。 やがて滝状の壁に出る。雪の下をかなり大量の水が流れていて、今にも底雪崩が起こりそうである。ルートファィンディングがとてもむずかしい。幾日か降り続いた雪が西壁の状態を最悪にしているのだ。高度が下がるにつれて氷が消え、ベタ雪が多くなる。それも岩の上に薄くかぶさったベタ雪なので、ピッケルが効かない。アイスパイルを出し、ダブルアックスで下る。 アイゼンの爪が、カリカリと岩を食む。微妙なバランスを何ピッチも強いられる。太陽は沈み始めた。急がねばならない。だが、この頃よりMr.林、Mr.春両名共に疲労が激しく、何度ザイルを引いても動きが鈍くなる。 こんなに大量の雪をつけた西壁でビヴァークする事は避けるべきだ。雪崩と落石だけでなく天候の悪化も考慮しなければならない。「もっとスピーディに行動できないのか!」と問うと、「これ以上は無理だ」と答える。 |
 |
Page6 |
|---|
| しかし近くでよく見ると肉体的な消耗はたいした事ない。精神的な疲労が大きいようだ。いつ果てるとも知れぬデリケートな雪壁の下降に、神経をすり減らしたにかも知れない。 ザックの重いのも応えているのだろう。だが、まだまだ動けるはずだ。連続20時間の行動は、日本でも何度かトレーニングしている。その時のザックはもっと重かった。ラッセルだって、もっとひどかったはずだ。 行動を続ける。右に大きくトラヴァースすると、又岩と雪のミックスした厭らしい斜面が続く。柄に爪の付いた特製のアイスパイルが、身体を支えてくれる。この壁が最後の雪壁で、後は大きな広いガラ場になる。 アイガーグレッチャーがはるか遠い下方に見える。ここでアイゼンをぬぎ、左へ左へと逆にトラヴァースする。右の西稜は、スパッと切れていて絶望的なのである。完全に暗くなる。 左の端は急な雪渓である。ルートらしく、闇の中にわずかにラッセルトレールが見える。だが、ためらいたくなるような長く急な雪渓だ。 |
ヘッドランプを付け、再びアイゼンをはき、ダブルアタックスで300mも下った頃、突然、叫び声が聞こえた。下方を見ると先行パーティの3人が滑落していく。 ヘッドランプの明りだけが、ぐるぐる回転しながら、闇の中に落ちて行く。「止めろ、止めろ」と叫んでいる声がひびく。雪渓の下部で止まったようだ。 しばらくすると立ち上がり、又歩き始めた。たいした事はなかったようだ。やがて雪渓の傾斜はゆるくなり、滝のような段になった岩場に出る。グレッチャーの駅はもうすぐであるが、この岩場をスムーズに下る事ができるのか? 最後の最後までアイガーは我々の行く手をさえぎる。岩にへばりつき水を飲む。「うまい」ものすごくうまい。何十遍、何百遍、こうして雪解けの水を飲んだ事だろうか。いつだってその時が一番おいしかった。 しかし今のこのうまさはやっぱり極上だ。途中でも何度か雪を口に含み、又は岩場にしたたる水に口をつけ下ってきたのだが、こうしてまとめてゴクリとやると、ほんとにうまい。 時計を見ると、10時を過ぎている。すぐに腰を上げ、右に左にルートファィンディングしながら滝状の岩場を下る。再び雪の上に出ると、グレッチャーの駅であっ |
た。駅と言っても幾つかの建物があるだけで、氷河と岩に囲まれた静かな地である。 一番電車が出るまで大分時間があったので、早朝のアルプをクライネシャィデックまで歩いた。昨夜、降りてきたアイガーの西壁は雲の相間に、信じられないような急峻な雪壁を見せていた。 |
 |
Page7 |
|---|
|
カフェテラスの寝椅子に長々と寝転び、今日最初の太陽に身を浴した。谷間からホルンの音でも響いてきそうなアルプスの朝であった。ひと眠りするとレストランが開いたので、ビールを飲み、ゆっくりアルプを下った。 |
グルントの駅の近くを流れる川に、氷のかたまりがたくさん浮いていた。大きな雪崩があったのだろう。テントに帰ったのは昼近くであった。2日間満足に食べていないので、猛烈に腹が減っている。ジャガイモをどっさりゆでて、マヨネーズとミルクで食べた。 |
ジャガイモの皮をむくのももどかしく、息もつかずに食べ、ミルクを流し込んだ。ずいぶんといろんな料理を食べたが、「ヨーロッパで一番おいしかったものは?」と聞かれたら、僕は即座に「アイガーのジャガイモ」と答えるだろう。 |
 |
Page1 |
|---|
|
マッタ―ホルン登頂記 |
けれど、とうとうやってきた。雲一つないものすごい快晴である。昨夜はテントの内側に氷が張った。大陸的な大きな高気圧が張り出したに違いない。溢れる太陽の光の中で、ゆっくり朝食をとる。何とも良い気分であり、マッタ―ホルンの頂きをまだ踏んでいない事を除けば精神的にも充分満ちたりているのである。
アイガーの下降時、Mr.春はもう山には登らないというような事をしきりに言っていたし、技術的にも体力的にもまだ無理なようなので、テントキーパーになってもらう事にした。こんな決断はとても苦しいのだが、アクシデントは絶対に避けねばならない。 食糧を買出ししながらヘルンリ小屋へ入る事にした。ザックを担ぎ、まず、果物屋に入りドライフルーツ、ナシ、リンゴを買い、それからパン屋に入りケーキパンを買う。何しろグリンデルワルトでの黒パンにはひどい目に会っているので、食べられる自信のあるケーキパンにしたのだ。そうそうあの黒パン、食べる者がいなくて、とうとうツエルマットまで運んだのだが、今朝開けてみたら黴が生えているので捨ててしまった。あーあ、もったいない事をした。PTT(郵便局)にも寄った。 |
キリ君へのツエルマット第一報を出そうと思ったのだが切手を売ってくれないのだ。入口の自動販売機を使えと言うのだが、これが又80サンチームの切手がなくて、40サンチームや30サンチームの小さいのばかりで困るのだ。 狭い絵葉書の上に何枚も切手を貼るわけにはいかないのだ。2フランで5枚ぐらい組み合わせになった記念切手を売っていたので、それを買って出した。ヴィスプ川に沿って、左岸を歩いて行ったのだが、どうもケーブルの駅は反対側らしい。 少し戻り、右岸に出て歩いて行くと、スキーヤーがスキーを担いで、何人も通る。何だか表示のはっきりしない駅で、このケーブルに乗ると、何処へ行くのかがさっぱり解らないのである。フーリーで乗り換え、シュワルツゼーに出る。 フーリーからはもう一本、トロッケナーシュテークにケーブルが出ている。シュワルツゼーは良い所である。ぐーんとマッタ―ホルンが近づく。あたりは視界を遮る物もなく、広々としたアルプの彼方に白銀の峰々が連なる。 |
 |
Page2 |
|---|
| ワリスアルプスの主峰モンテローザ(4638m)、その裾を流れるゴルナー氷河とフィンデル氷河、フィンデル氷河の左にはドム(4545m)、更にその右にリンビッシュホルン(4190m)シュトラールホルン(4190m)。ゴルナー氷河の右にはリスカム(4538m) そしてブライトホルン(4160m)更に右の台地はイタリア、スイスにまたがる大スキー場テオドールパス、テオドール氷河をはさんでマッターホルン(4477m)の黒い角が頭上を圧する。 その右にダンディラン(4171m)、チナールロートホルン(4221m)、ワイスホルン(4512m)と白き峰は迫る。実に雄大なパノラマである。氷河の湧き水で出来た池がある。 あそこにテントを張って、のんびりと日光浴したり読書したり、飽きたら池に映える白銀の峰々を眺めて暮らしたら、ずいぶんと豊かであろう。わずかにヘルンリ小屋が見える。 レストランで食事。セルフサービスなので、美味しくてボリュームのあるものを選んだつもりだが、食べてみると酸っぱいものばかりで参った。大ジョッキーの生ビールは美味かった。 |
かなり退屈な登りがヘルンリ小屋まで2時間程度続く。途中たくさんのハイカーに会う。小屋は頑丈そのもので良い小屋だ。日本のようなペラペラ小屋からは想像もできない。料金は23フラン、ベッドは17番であった。 外に出ると、夕日がマッタ―ホルンの頂で輝き、逆光の中に黒くホルン(角)が浮き出ている。ソルベイ小屋に泊まるのであろうか。2,3パーティが、ヘルンリ稜に取り付いている。小屋には、いかにも利口そうなセパードが1匹と、白い犬が1匹いた。 棒きれを谷に投げると、急なガレ場をものとせず、取りに走るのである。すごいクライマーだ。隣は食堂になっている。ミルクを飲む。2度目に又頼むと、その場で「飲み干せ」と言って1杯おまけしてくれた。ステーキも頼んで、ホルンを仰ぎながら外のテラスで食事をとる。 3時間前食べたばかりなので食欲はないが、明日は早い。それに、たぶん明日の行動も連続10数時間を越え、満足に食事もできないだろう。たくさん食べておこう。 |
2時間程微睡み、空を見るとわずかに明るかった。小キジをうちに外へ出た。8時半である。暮れなずむ山々の赤と、眠りに入った谷の暗い静けさが、群青の空の下にあった。ベッドに入ったが、すっかり目が覚め、眠れなくなってしまった。 30分、1時間とずんずん時間が経つ。一から数える。千まで数えても眠れない。焦る。明日の行動に大きくひびくのだ。早く眠らなくては!また数を数える。・・・・明日、雪は降るであろうか・・・・ 眠い。だが起きねばならない。天気は?大丈夫、快晴らしい。 食欲はほとんど無いのだが、ミルクだけは美味い。どうも他の連中の食ってる物が、やたらうまそうに見える。ポットにお湯を2人分出してくれた。紅茶を飲んで、ケーキパンを無理矢理流し込んだ。さあ出発だ。だが、気が重い。 まだ午前3時の闇に眠っている岩場でいったいルートファインディングは可能なのだろうか?外へ出ると、数パーティがすでに岩稜に取り付いている。ヘッドランプの光だけがチラチラ動く。。 |
 |
Page3 |
|---|
| グリンデルワルトで一緒になった、3人の日本人パーティも出発の準備をしている。もたもたしている3人のスイス人を追い抜くと、やっと明るくなってきた。上のパーティが石を落とす。「やばい、大きい」するとすぐ下にいたパーティのトップがひしとその岩を抱き止めた。 かなり危険な行為である。だが、その岩が落ち続けたら、勿論もっと危険であることは間違いない。日本の山では信じられない行為である。ザイルの後には女の子がいる。トップの彼はガイドなのかもしれない。稜通しにつめてきたが、ここでルートは第1ルンゼにぶつかる。 ルンゼのトラバースに数パーティが集中している。ルンゼは浮石が多く、岩もボロボロで落石が頻繁に起こっている。石の落下距離を小さくし安全を保ち為、先行パーティのラストにぴったりと付き追い上げるようにして登る。 彼のヘッドランプはつけっ放しだ。夢中で登っていて気が付かないのであろう。「オーイクスペンシブ!」と注意してやると「ダンケ」と言って嬉しそうにニッコリ笑った。スイスに着いて1週間ぐらいは話す前によく考え作文してから話しかけたが、近頃は慣れてきて自然に何か単語が飛び出してくる。 |
その単語が英語であろうと、仏語、独語、はたまた日本語であろうと何となく通じるから面白い。 どうも最初からルートを間違えたらしい。下を見ると、ルンゼの下にルートがあるようで我々より遅く出発した日本人パーティがいる。 稜通しに登らずに東壁側をトラバースすれば良かったのだ。他のパーティと一緒にルンゼを少し降りて、一般ルートに戻る。ソルベイ小屋に泊まった連中だろうか、もう降りてくるパーティもある。3人の日本人パーティは外人グループを抜きながら早いピッチで進む。 このあたりより、ずっと前になり後になり2つの日本人パーティは合同体のような格好で高度を稼ぐ。ゼイゼイハーハーしながらも我々は調子良く、アルプスの標準タイムを上回る早さで登攀を続けた。 やがて昨日ヘルンリ小屋にいた二人の女の子と男の子のパーティに追いついた。ハイカーだと思っていたけどザイルを組んで一応登っているようだ。これで全部の日本人パーティが合流したことになる。 |
しかしこのパーティは遅いのですぐ追い抜いてしまった。途中で頂を断念して下山したようである。下りには姿を見かけなかった。合流はほんの一瞬で、我々は休息をとらず2つの日本人パーティを後に残し東壁側にルートをとった。 しばらく進むと先程落石を受け止めたパーティに追い着く。ザイル操作のやりとりを聴いていると「ジャネット!」という呼び声が良くひびく。ザイルパートナーの女の子の名前らしい。 ラストのジャネットの後にぴったり付き、追い越すチャンスを伺うが、なかなか抜けない。ジャネットはニッカ―ホースをはかないで登っているので、脚が直接アルプスの冷気に触れている。金色の産毛に小さな水玉が付き、そこに今生まれたばかりの透明な朝日があたる。 殺風景な黒々とした岩ばかりの世界で、ジャネットの脚だけが息づいていた。ジャネットのパーティも抜き、我々がトップでソルベイ小屋に着いた。ミッテルレギの小屋を小さくしたような良い小屋である。 |
 |
Page4 |
|---|
| それにしてもすごい所に建てたもんだ。平らな場所が全然ないのだ。岩稜の切り立ったほんの少しの窪みを利用し、小さな箱を置いたような光景なのだ。ヨーロッパでは山小屋を建てられるような、平坦で雪崩からも安全な場所なんて無いのだろう。 小屋直下の氷のトラバースはアイゼンがないと少し苦しい。トラバースに続くモズレイスラブはホールドが細かく岩登りらしい感じが味わえた。小屋にはソルベイ爺さんの写真が飾ってあった。ヨーロッパ人は写真を飾るのが好きなのかなー。 ここまでノンストップで登ってきたので、少々荷の重さが気にかかる。ソルベイ小屋に不必要なものを残していく事にしたが、ここで失敗した。というのはここまで寒さを感じなかったのでオーバーズボンをつい置いてきてしまったのだ。小屋を出て頂きに至る赤い岩壁に出ると、突然風は強くなり寒さが厳しくなった。 羽毛服を着たのだが下半身が寒く凍り付きそうであった。マッタ―ホルンでの危機は二度あった。もう一回は下山中に気がついたのだが、東壁の中の落石のものすごさである。 |
ヘルメットはテントに置いてきてしまっている。上部のパーティが石を落とす。自然落石がそれに加わる。しかしルンゼを下らねばならない。ほんとにこの時は命がけであった。最後の急な壁は近そうでいて決して近くはなかった。 ほんのあと少しという感じはするのがだが、実際には、ヘルンリ小屋とソルベイ小屋間よりも時間がかかった。岩場の傾斜は急になり、氷と雪が増え、太いフィクスロープが目立ち始めると、先行パーティが次々とつかえ、時間待ちが多くなる。氷は完全にカリカリである。 平らな場所が無く、苦しい姿勢でやっとアイゼンをはく。ジッヘルするにも、ピッケルが刺さらず、スリップしないように動く。今まで、ルートはほとんど東壁側にとってきたが、ここで北壁側の右にに移る。東壁側は完全にオーバーハングしたフェースであり、ツェルマットより仰いで見ても、絶望的な感じである。 北壁側は雪と氷のルートであり、アイゼン無しでは動けないのであるが、氷壁の途中に止まっているパーティは、アイゼンをはいていない。 |
そのため完全に動きがとれなくなり、ピッケルでカッテングしながらアップザイレンを試みている。見ていると実にあぶなっかしく、今にも事故が起きそうである。氷壁の上部に出ると誰もいなくなった。 この長い氷のルートで立ち往生し、頂きを断念したパーティが、多かったのかもしれない。アイガーの時のような静けさが戻ってきた。この氷と岩のミックスした壁の上には、群青の空しかない。 たぶんマッタ―ホルンの頂きに違いない。一歩一歩アイゼンを蹴り込む。 7月27日午前11時 4478mの頂に立つ。頂には誰もいなかった。 どうして涙を流したのか解らない。今までに一度もなかった事であり決して今後もあり得ないだろう。 山の良さはいつも追想の中にある。頂に立った時はいつだって、空腹と疲労と下降の不安でいっぱいだ。なまっちょろい感傷の入り込む隙間なんか、ありゃしない。疲労もせず、楽々と登れるような頂に立ったら、歓びの方がお断りするだろう。 |
 |
Page5 |
|---|
| アイガーの頂に立った時なんぞは、これからもう一つの、もっと苦しい山に出かけるような気分だった。映画では頂きで抱き合うシーンがよく出てくるが、あれは頂で行う作業の一つであって、自然な感動のなせる業ではないのだ。 ほんとうの歓びは、いつも追想の中にある。それなのに、この時はほんとうに泣けてたまらなかった。ザイルを手繰る毎に近づくMr.林に見られそうで「おい!泣くな、やめろ」と何度か言いきかせたのだが、涙が勝手に溢れ出てくる。 「こんな山、日本の富士山みたいなもんじゃないか!」富士山に登って泣く奴あるか!」などと説得する声までもが震えている。そうだ小さい頃、僕は泣虫だったんだ。小川未明の童話を読んではよく泣いた。今だってほんとは泣虫なんだ。 Mr.林のげっそりした苦しそうな顔を見たとたん、なまっちょろい感動は去った。イタリアの頂を踏もうと声をかけるが、彼は「動きたくない」と言う。8ミリを頼み、一人で十字架の向こうのイタリアの頂まで行った。石を拾った。イタリアのピークで七つ。 |
スイスのピークで七つ。再びこの頂を踏む日は来ないかも知れない。
正午に下降を始めた。ぐんぐんザイルをのばす。だが、Mr.林調子悪く、ピッチは上がらない。頂上直下の氷壁を過ぎると、又、幾つものパーティに会う。フィクスロープのある所では必ず数パーティがもたもたしている。 |
焦る。「あった」折れたアイゼン。確かに登りに通過したルートである。 赤く錆びて折れたアイゼンには見覚えがある。だがそこはルンゼになっていて、特に落石が集中しているでは。ヘルメットはテントの中だ。 役立たずめ!意を決し、ルンゼのトラバースに走った。もちろん走っていると感じているのは意識だけで、実際はノロノロしていたにちがいない。ザイル一杯に進み、Mr.林を待つ。視界にあった先行パーティは、左側のヘルンリ稜に消えた。 ザイルを引っ張るが、Mr.林の動きは遅い。ソルベイ小屋まで3時間もかかってしまった。アイガーの時よりも調子悪そうである。しかしあと3時間でヘルンリ小屋まで降りないと、今日中にツェルマットへ下るのが難しくなる。 テントキーパーのMr.春には、27日中には必ず帰ると言ってある。すぐに小屋を出る。長い長い岩場の下り。ルートファインディングに迷い落石に気を配り、単調で危険な作業を続ける。登る時には感じなかったが、今、改めて東壁の広さに驚く。 |
 |
Page6 |
|---|
| 広大な岩壁が下部のクレパス帯を隔てて、緑のアルプへ一気に落ち込んでいる。
6時、ヘルンリ稜の下部に着く。ザイルを解く。老ガイドが待っていて固く手を握ってくれた。「メルシイ」心をこめて応えた。メルシイ、良い言葉だ。風格のあるガイドで、いつも遠くを見つめているような瞳であった。Mr.林には「Very tired!」と、優しい言葉をかけていた。 日没まで2時間、ここからツェルマットまで5時間のコースだ。明るいうちにツェルマットに戻る為には、どうしても2時間で下らねばならない。 |
ゴンドラの止まってしまったアルプの牧場を、風のように走って、あの緑の谷に帰りたい。そして、夕闇の中に沈んでいくマッタ―ホルンを静かに見つめてみたい。
夕焼の空に黒いシルエットを落とすマッタ―ホルンを背に走った。シュワルツゼーまで40分、ここからは緑の海だ。バラ色に染まるアルプスの峰々に囲まれた草原に羊の群れが佇む。首に下げた鈴の音が透き通った大気の中を何処までも流れていく。 |
最初の泉では跪き音をたてて水を飲んだ。ツェルマットの谷に一つ、又一つ灯がともる。雪の峰はバラ色の微笑を捨て、冷たい灰青色に変わった。森に入ると、樹間からの斜光が幾筋も糸を引き、思い思いの場所を照らしては細い溜息を吐いて消えてゆく。 最後の一筋が消えると、寡黙な闇が森を包み始める。2番目の泉は、かすかな薄明りの森にあった。バンビが佇んでいた。鹿の子斑の白がぼおっと浮かぶ。振り返ったバンビと一瞬目が合った。だが、次の瞬間には、決して手の届きそうもない深い闇の中に消えてしまった。 |
まして、白き峰々に囲まれたアルプの牧場に、羊や草花を訪れれば、 ハイジやペーターやヨーゼフが、僕を放っておくはずがない。 手をつないで、毎日アルプを駆けめぐった。 あんな堅苦しい表現になってしまったけれど、高山植物の一覧表は、ほんとはその時、 一緒に遊んだ友達の名前なんだ。 それならそう書けばよいのだが、どうしても書けなかった。 それは、たぶん現在、僕がメルヘンの世界の住人ではないからなんだ。 幾らこの冊子のページをめくっても、Mr.坂の文章には、ハイジはもちろんヨーゼフだって出て来やしない。 追想に浸り、メルヘンの世界に再び飛び込んで、 あたりいっぱいに溢れるキラキラする仲間達を捕まえて、原稿用紙の上に並べようとしたけれど、 どんなに目を閉じても、メルヘンの世界は復活しなかったのである。 『もしかすると、あれは幻想でしかなかったのかもしれない』そう考えると、とても淋しい。
|