
ヌン峰西稜インドヒマラヤ・・・劫の彼方へ
(報告書・ヌン峰より抜粋)
記録:坂原忠清
鮮烈な存在感 |
8日間の短期速攻 ABC設営後8日間の短期速攻登頂であったため全員高山病に苦しめられ 起床安静時心拍数100前後での行動が毎日続きました。 アタック前に一度BCに下り休養をとらねばと思いつつも、 高所ポーター無し隊員4名のみの荷上げではそうもいかず連日行動を余儀なくされ、 疲労を蓄積したまま雪の舞い始めた最終キャンプC3(6400m)に入りました。 「いよいよ悪天周期突入か」と一時は長期戦を覚悟しましたが、 どうにか翌15日登頂を果たすことが出来ました。 |
|
日印絵画交換会 隊長 坂原忠清 |

| Contents | |||
| ヒマラヤ登山記録 | チベット | 1998~2006年 | |
| 《A》 | ヨーロッパ・アルプス(アイガー、マッターホルン、モンブラン) | スイス、フランス | 1975年7月~8月 |
| 《B》 | コーイダラーツ初登頂(5578m) | アフガニスタン | 1977年7月~8月 |
| 《C》 | ムスターグアタ北峰初登頂 (7427m) | 中国 | 1981年7月~8月 |
| 《D》 | 未知なる頂へ (6216m) ビンドゥゴルゾム峰 | パキスタン | 1979年7月~8月 |
| 《E》 | ヌン峰西稜登頂 (7135m) | インド | 1985年7月~8月 |
| 《F》 | ナンガ・パルバット銀鞍 (8126m) | パキスタン | 1983年7月~8月 |
| 《F2》 | ナンガ・パルバット銀鞍 (8126m) その2 | パキスタン | 1983年7月~8月 |
| 《G》 | ナンガ・パルバット西壁87 (8126m) | パキスタン | 1987年7月~8月 |
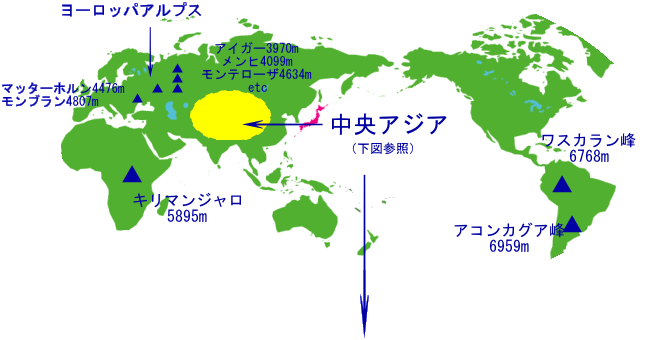
中央アジア遠征峰
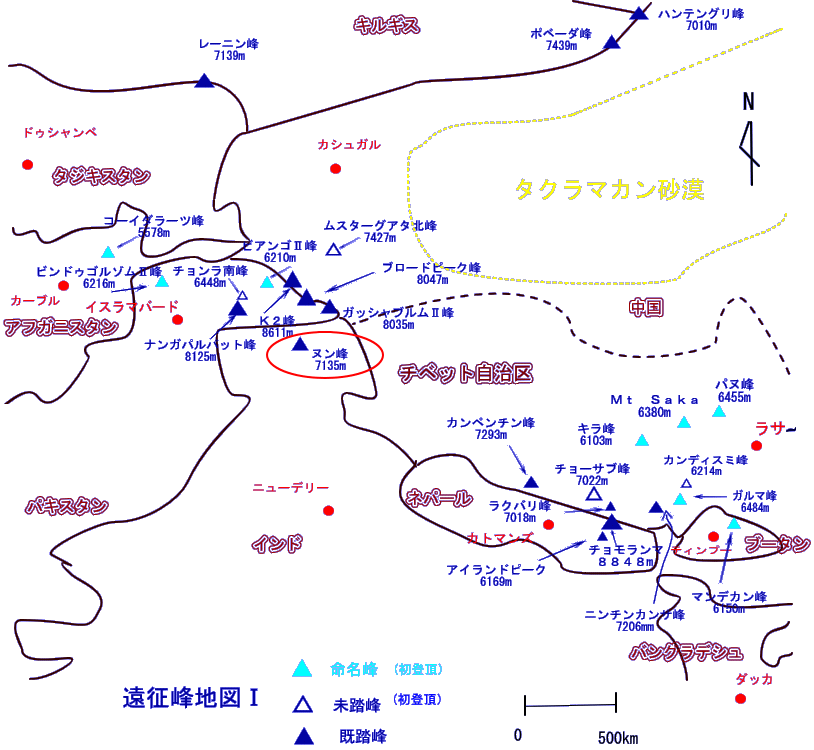 |
![]()
1 劫の彼方へ
序
仏教を生んだインド亜大陸は、地球上の地理的条件を総て備えた世界のニミチュアであった。
ヒマラヤの極寒から南の熱帯雨林まで広がる亜大陸は、
大陸との境界を高峻なヒマラヤ山脈によって遮られ、ベンガル湾とアラビア海に行手を阻まれた人間界の小宇宙であった。
小宇宙には多種多様な民族が雑居し、彼等の生活を支える大河は、
いずれも遥かなる高み、神々の住むヒマラヤを源泉としていた。
インドヒマラヤこそ神々の座であり、仏教宇宙の出発点であった。
インドヒマラヤの北西部、カシミール地方の最高峰ヌン(7135m)の短期速攻による全員登頂を終えた今、
鮮やかに、神々の座よりもたらされた思惟の波紋が私の胸に甦る。
 |
Page1 |
|---|
|
(1)山麓へ ヌン峰の魅力は、バニカルで遠望する雪と氷を纏った孤高の容姿から始まり、やがてそれはタンゴールからの草原キャラバンルートの山麓美へと引き継がれる。 残念なことにキャンプサイトの見晴らしは良くない。南北に走る尾根に遮られ、南はセンティック峠の雪山がわずかに見える程度である。時たまピアと呼ばれる鳴き兎が、甲高い声で鳴く。キャンプサイトには、石を積んだポーターの無蓋キッチンが作られている。 |
(2) 悠久の断層 ABCの東は上部雪原へ出るアイスフォールに遮られ、西はセンティック氷河下流となって落ち込んでいる。このアイスフォールの中からABCを取り囲む岩壁群を眺めると、壮大な地表が刻む悠久の海に飲み込まれてしまう。 (3)閻浮提 エコーはエコーを呼び、加速され渦を巻き、星雲となり、インド亜大陸をコアにした宇宙創造のドラマを語り始める。「閻浮提(Jamba-dvipa)と呼ばれる人間の住む世界あり。その北に雪山(Hima-Vat)あり。 |
雪山の更に北に無熱悩池(Anavatapla)ありて、この地よりガンジス河、オクサス河、インダス河、シータ河が東西南北の流出口、銀牛口、瑠璃馬の口、金象の口、玻瓈獅子の口から流れ出ず」(具舎論) 創造のドラマは、5世紀のインド人が認識していた地理的世界から始まる。閻浮提は逆三角形をしており、インド亜大陸そのものといえる。 インド亜大陸である閻浮提は、金輪上の八つの海の一つに浮かぶ、東西南北四つの島のうちの一つで、南に位置する。金輪は巨大な水輪によって支えられる。水輪は更に巨大な空間、風輪によって維持される。 |
 |
Page2 |
|---|
(4)三阿僧祇劫 まず彼等は途方もない宇宙を捕えるため、そのメジャーである時間を認識の支配下に置こうと試みた。 1億年を数えるには100万個の芥子粒が必要になる。平均的な大きさの芥子粒ナガミヒナゲシの直径が0.8ミリであるから、100万個の芥子粒の体積は100万の立方根の0.8倍の3乗、およそ512㎠となり、(7.4×105)3÷512≒7.9×1014億年
つまり7.9×1022年となる。 |
(5)風輪 三阿僧祇劫まで認識の翼を広げ、初めて為す術のない虚空を見たのと異なり、空間に関しては、最初に手の届かぬ異次元を仏教は設定した。 5世紀の小乗仏教の綱要書「俱舎論」は、異次元の虚空に風輪を浮かべた。円盤状のこの世界は、円周が「阿僧祇」由旬、つまり10の59乗由旬、厚さが160万由旬ある。 となる。現代の科学では、宇宙の果てが150億光年、直径が3.0×1010光年とされているので、この風輪の直径は光を手段として認識し得る宇宙の直径の8.3×1035倍ということになる。 つまり風輪の大きさを現在の宇宙と同じ大きさに縮小して考えると、ほんものの宇宙は1億分の3.4㎝にしかならないということである。 |
仏教が認識の彼方で遭遇した虚空とは、何であったのか? (6)虚空 生物は、その種が持っている観測手段によって、認識限界を決定する。従って当然、アミーバ、アリ、イルカ、ノスリ、人類等の認識世界は、各々異なる。 光の世界を一億分の3.4㎝に閉じ込めた巨大な風輪。その風輪を浮かべた、超巨大な虚空。我々が、無限と認識している光の世界は、実は、点以下の存在なのであろう。科学の発達を待たずして、時を越えて認識した虚空に、仏教は何を見たのであろう。 |
 |
Page3 |
|---|
(7)他化自在天 「俱舎論」は、風輪の上に水輪を乗せた。水輪は、直径120万3450由旬、厚さ32万由旬の円柱である。その上に厚さ32万由旬の、同じ直径の金輪を乗せ、その表面に、海、山、島を作った。 平面である金輪上には9つの山があり、中央に須弥山がある。高さは16万由旬で、半分が海中に没しているので、標高は8万由旬、約59万㎞である。エベレストの60万倍以上の高さであり、地球の直径の47倍にも及ぶこの山は、到底地球上の存在とは考えられない。 須弥山の山頂から8万由旬上空に空中宮殿があり、夜摩天が住んでいる。更にそこから16万由旬に天空があり兜率天が住み、その2倍の32万由旬上空に楽変化天の天空があり、そこから更に2倍の64由旬の上空に他化自在天が登場する。 つまり、虚空に浮かぶ仏教宇宙の上下は、風輪から他化自在天の住む天空まで400万由旬、2960万㎞、光速で100秒ほどの距離内に収まるということになる。風輪の直径に較べると、ほとんど無に等しい厚さである。 |
(8)劫 スタテックで虚無的な、認識への絶望を抱きつつ、あえて仏教は虚空に対決しようとした。風輪を回転させ、無限の時間を与え、仏教宇宙の生成流転を計ったのである。 風輪の回転は、4つの段階を経て一回転を終わる。各段階は「劫」という時間の単位で呼ばれる。ビッグバーンによる宇宙の誕生、風輪の発生を「成劫」という。 57億7千万年後に、仏陀の次の救世主として兜率天から下るという、弥勒菩薩の出現の真の意味は、森羅万象の彼方にチラチラと見え隠れする虚空への恐怖を塗り潰し、偽りの、一時の平安を得るためのものではないのか。 いずれにしても、現代の最先端を行く科学理論ですら予想をためらっている、ビッグバーンとブラックホールによる宇宙の生成と消滅の構造を、仏教は、1500年も前の5世紀に認識していたのである。これだけでも、仏教が本質に対する鋭い透視力を持つ、得体の知れぬ知性であることに、気が付く。(9)劫の彼方へ 私の登山は、恐ろしい深遠、虚空の呼び声を聴いた時から始まったような気がする。もちろん最初は、その声の正体が何であるのか見当もつかなかった。青春前期の、誰もが陥るひどく虚無的な感覚の中で、総てを越えて尚真実たり得るものを求め、より遠くへ視線をさまよわせた。 |
アレクサンダー、ダリウス、ジンギス汗といった世界史の名優達が目指していたものは、内なる地平線であり、その行為こそ正しく生命の軌跡であると強く実感したのは、初めて中央アジアに足を踏み入れた1977年のオクサス河(アムダリア)上流に遠征した時であった。 「人類は個体を越えて次々と、虚しく地平線を目指し、何処かへ行こうとしている。」この発見は私の登山体験とオーバーラップし、奇妙な興奮を私にもたらした。 更に数回、アジアの山々を訪ね、虚空の呼び声を聴き続けた。アフガニスタンで聞いた呼び声は、チトラルやカシュガルでエコーし、ナンガーパルバッドの断層で視覚化され、今回のインドヒマラヤで、仏教宇宙の彼方へ帰結した。 激しくのたうち、呻きながら、時を累積していく地表の生の姿を目の前にして、「劫」の意味するものがなんであったか、今こそ明瞭になった。1劫、790垓年という、途轍も無く長大な時間は、やがて虚空に吸い込まれ、無に帰してしまう、宇宙の虚しい守護神であり、仏教宇宙論の最後の足掻きであった。 光すら存在しない虚空の呼び声というのは、総てのエネルギーが平衡状態になる熱エントロピーの死への誘いであり、森羅万象にささやかれる終焉へのサインなのだ。 劫の彼方への出発こそ、生命が真に意図するものなのかも知れない。 |
2 ヌン峰への経緯
 |
Page1 |
|---|
|
(1)3月槍合宿談義 これが「ブータン計画」3度目の合宿のスタートであったが、まさかこれが今計画最後の合宿になるとは夢にも思っていなかったのである。最高峰であり未踏峰でもあるガンケールプンズム(7541m)への登山許可の申請をブータン政府に出したのは、ブータン登山解禁の2年前にあたる昨年である。 当日、ブータンの美しい衣装キラで着飾った女性達の侍る総会に出かけると、桑原先生の他「秘境ブータン」の著者、中尾佐助氏、当会の隊員の凍症でお世話になった聖マリアンナ病院の長尾梯夫氏達が役員会を開いていた。 しかし、3月いっぱい待ったが、返事なし。今秋にはアメリカ隊と北海道HAJ隊の2隊にガンケールプンズムの許可が下りているのでその前の8月に許可をもらうのは困難であると予測していた。 |
(2)ブータン計画頓挫 翌日、やっと雨が上がり滝谷が朝日を浴びて眩しく光る。穏やかな槍沢と異なり飛騨沢はデブリが山を成している。雪崩の通り道は高さ2、3mの氷の垂壁両側にできている。この壁を越えて中崎尾根に取り付く。 槍の穂先は昨日の雨でヴェルグラが張り付き、岩という岩は総て氷と化している。ピッケルでぶったたき氷を剥がしながら登る。途中で道無き岩場を下降してみたが、とても悪く絶妙なアイスクライミングを強いられ、久しぶりに冷や汗をかいてしまった。 停滞を希望する深瀬に、徳沢までのビールの買出しを頼んで岡林と涸沢へ出かける。誰もいない雪の涸沢カールは素晴らしい。北尾根の岩稜も奥穂の胸壁も北穂の東陵も、まるで小さなヒマラヤである。 |
(3)インドヒマラヤ検討 「まだ私は高峰登山の経験が無いので、できれば7千mのピークを踏みたいですね。」「夏までに残された準備期間は3ヶ月しか無い。この短期間で登山許可のとれる7千m峰といえば、パミールのレーニン峰、コミュニズム峰、コルジュネフスカヤ峰の3峰か、やや低いがアラスカのマッキンレーぐらいだろうな」 「インドヒマラヤのヌン峰なんかどうでしょうね。7千m峰にしてはアプローチも短いし、ルートも比較的良く知られていますし。5年前にヌンの近くに私、入ったことあるんですよ」「IMFは日山協の推薦状を必要としないから、今から手続きをすれば間に合うかもしれんな。やってみるか?」 予期した通り帰京してもブータンからは何の返事も来ていなかった。雪焼けで皮の破れたひどい顔でHAJの事務所に顔を出すと、吉田憲司氏が居た。イスラマバードのサミー氏の所で働いているはずなのにどうしたのか聞いてみると、あそこで働く話はだめになって今HAJの事務局で働いているとのこと。 IMF手続きの中で最大のネックは入国査証である。査証の取得までにふつう3ヶ月かかるらしい。今4月である。3ヶ月後というと7月になってしまう。査証申請の前にIMFから登山許可をもらい登山料をインドに払い込まねばならない。 ヌン峰は最近、特に脚光を浴びるようになった人気のある山なので、各ルート共すでに他の登山隊に許可されている可能性が高い。そうなると1ルート1隊許可制のIMFが許可を出すはずがない。 |
 |
Page2 |
|---|
|
(4)インド登山協会との交渉 「今月(5月)の中旬にダージリンで会議があって私も丹部さんも呼ばれている。私は行けるかどうかわからないが、丹部さんは出席するので私から丹部さんに許可と査証の件を話してみよう」 丹部氏は日本山岳協会の副会長で私も何度か会っているが、あまり良い印象を持っていない。中国のムスターグアタ北峰(7427m)を2週間で登る計画を立て、名古屋大学の低圧室でトレーニングをしたり、ステップテストの効果的な方法を研究したり、悪戦苦闘している最中に丹部氏より電話がかかってきたことがある。 「2週間で7500mの山が登れると考えているのか。最近ヒマラヤの死亡事故が非常に多い。高山病による滑落や初歩的なミスが多い。外務省からも文句を言われている。高所順応はどうするのか? 原さんに相談して名古屋大の低圧室に入ったらどうか」
|
というような内容であった。カチンときたことは言うまでもない。1979年の遠征では隊員の一人が高山病で倒れ、パキスタン軍のヘリコプターを要請したが事故地点が高く役に立たず、危機一髪で我々だけの力で救助したり、アフガニスタンやアンデスでも苦しい体験を重ねている。 と答え電話を切った苦い思い出がある。したがって川崎氏より丹部氏の話が出ても乗気にはなれなかったのである。この後、私は丹部氏への認識が誤っていたことに気付かざるを得なかった。 |
その後も査証の件や遠征終了後のポータートラブルの件でも積極的に動いてくれ、その仕事の早さと面倒見の良さに驚かされた。あの電話の真意は持前の面倒見の良さから出たもので、山岳協会の推薦状を必要としない中国遠征に対しての副会長の権力的介入ではなかったのである。 後日、一緒に飲んだ時、丹部氏にこの話をして誤解していたことを詫びたのだが、かなり酔っていたので、はたして丹部氏は覚えているかどうか? ダージリンの会議ではインドのクマール氏とブータンのジグミ氏の二人に会い、ヌン峰とガンケールプンズム峰の件について丹部氏は我々の意向を伝えてくれた。その結果、ガンケールプンズムは来年以後にならざるを得ないが、ヌン峰については査証の件を含めてどうにか今夏実行の目途が立ったのである。 それは雪の涸沢で岡林と二人で話し合ってから1ヶ月後のことであった。さあ、出発まで残りは2ヶ月。ガンケールプンズムからヌン峰への転進なるか? |
3 アタック前夜
 |
Page1 |
|---|
|
アタック前夜
|
ザンスカールの南を隠す一面の雲海はヌンを境にして、スッパリと断ち切られる。ヌンから北の空はいつも明るく、北西にナンガ―パルバット(8126m)、真北にK2(8611m)が白く輝いている。 カラコルムに進入するベンガル湾のモンスーンを遮り、ヒンズークシュやカラコルム、そして中央アジアを砂漠化する巨大なヌン山塊。風に舞う雪がその最後の巨壁を乗り越えられず、ヌン上空で低迷する一片の千切れ雲である事を祈りたい。すぐ北の空は晴れていると信じたい。 そうなると数日間は風雪に閉じ込められ、西稜核心部に張った固定ザイルは総て雪と氷の中に消えてしまう 胸ポッケの気圧計の針を確かめる。6400mをわずかに越えている。気圧が下がりつつある。 |
。雪崩も降雪直後から牙を剥いて、テントを襲い始めるであろう。一日毎に最終キャンプからの脱出は困難になる。低気圧襲来ならば食糧制限どころの話ではない。 |
 |
Page2 |
|---|
|
田村が岩野の二の舞を、踏む可能性は高い。田村は岩野の場合と同じく高峰登山は初めてで、高所に於ける生理データーが無く予測が難しい。
|
田村に余分な心理的負担をかける必要は無い。弱音を吐かず荷を担ぎ、人の2倍近く食べる田村には、まだ頂上に立てる力は残っているだろう。私はそう判断し、アタックには田村の大学の先輩でもある、面倒見の良い岡林とザイルを組ませることにした。 私のトレーニングは山行直前に行うインスタントトレーニングではない。年間を通じて走る。 |
山に入っている日以外は雨の日でも走る。雨の日は10階建てのマンションの階段を10往復走る。通常は約4㎞のコースに6つの坂を加えて走る。 飲み会で遅くなり二日酔いで身体に酒が残っている朝なんぞ地獄の苦しみである。それでも5時20分には起きて走る。錆びた5寸釘を足の裏に、深さ2㎝程刺した時も1日休んだだけで2日目からは、傷口から血を流しながら走った。この程度のトレーニングが毎日持続できぬような薄弱な意志では所詮、たいした山登りが出来るはずないのである。 |
 |
Page3 |
|---|
|
したがって決して無理なトレーニングを急に始めたわけではなく、この突然の激しい腰痛の原因に思い当たることは全く無い。放って置けば、いつものように自然に治ると思い1日待ってみたが回復せず。 「明日からヒマラヤへ行くので何とか痛みを取って欲しい」とお願いしたらドクターはこう言った。 「もちろん治しに来たのですよ。ヒマラヤに登りながら治すにはどうしたらよいか。大変興味あるテーマだと思いますが」 痛み止めと消炎剤をもらって次の日、飛行機に乗り込んだのである。この最終キャンプに入るまでも、いつ爆発するかわからぬ爆弾を抱えているようなもので、アキレ
|
ス腱と腰に神経を集中させ、びくびくしながら上ってきたのだ。登山に最も重要なアキレス腱と腰の痛みに耐え7千mの山巓に立てるかどうか私にとって今回の遠征の最大のテーマである。 しかし今までのところ、どうにかドクターに宣言したようにヒマラヤに登りながらの腰痛の治療に私は成功したようである。ABC(前進基地)からの連日の荷上げ、ルート工作にも耐え頂上までの残り7百mの標高差も気にならない。 |
我々はその部分をカットし、全遠征期間40日という短期遠征を成功させてきた。成功の一因は隊員の高所に於ける生理反応のデーターが、何回かの遠征を通して蓄積されていることにある。 しかし今回の隊員にはそれが無い。ブータン計画のために集まった高峰登山の経験の無い、新しい隊員だけで編成されている。3隊員の高所に於ける生理反応は、全くの未知数である。 ABC から8日目の明日、7135mの高さへ突入させることへの不安はどうにも拭いきれない。ベースキャンプまでは絶好調であった山口も、ABCに入ってから高山病の影響を受け始めペースが落ちている。 岡林はカルギルで発熱しダウン。回復後ABC への荷上げ中に、ふらふらになり意識を失う寸前までダメージを受けベースキャンプで寝込んでしまった。その後、仮キャンプ2とキャンプ2を設営し頑張ったが、キャンプ2(5800m)に入った夜は眠れず、一度高度を下げABCあたりで休養させる必要が岡林にはあった。 |
 |
Page4 |
|---|
|
本人もそれを希望しているようなので、岡林のメンバーチェンジも考えていたが、交換相手の田村の調子は悪い。私は風邪と高山病の影響で発熱し一度ベースキャンプからタンゴールの村へ下り、再び上へ登ってきたばかりでこれ又ベストではない。 |
高山病の典型的な症状、顔面浮腫はほとんど無い。各人共、頭痛は有るもののそうひどいものではないという。日中の安静時心拍数は私が65、山口、岡林が85。田村が100を越えているのを除けばたいしたものではない。 |
小さなテントの中で歌が始まった。静かなどことなく哀調を帯びた山の歌が次々と流れる。高山病の不安を抑えて大学5年生の田村が歌う。 多くの困難な山行を通して培われた山男の強靭な精神力が、いつも親密なパーティを生むとは限らない。自己主張の激突で空中分解する隊も多い。しかしこのテントの仲間は、強靭な精神力で自己を抑える術を知っている。それが苦しい高所テントの中でさえ、親しさを生み出せる原動力になっているのだろう。 |
 |
Page5 |
|---|
|
素晴らしい仲間が、加わったことを喜ぼう。そして若い彼等が私達の山行を乗り越えて、更に深遠な世界とめぐり会えることを期待しよう。 |
さあ、明日は7135mの 白い光の頂点に立とう。 |
4 アタック
 |
Page1 |
|---|
|
雪が止んだ。払暁の空には星も煌いている。首から下げたバロメーターを見る。気圧に変化なし。少なくともこの時点では、神は我々に味方している。アタック決行。 |
オーバーズボンをはくか、はかずにザックに入れるか瞬時迷う。薄いタイツ1枚と毛のズボンをはいているが、このままでは7千mの冷酷な風は耐え難い。だが、行動さえしていれば寒気そのものは、耐えられぬものではない。 |
それなくしてヒマラヤの山巓に達することは出来ない。常に死の臭いは行為に優先する。しかしアタックの朝だけは死と行為が逆転する。下界の日常性の中では決してあり得ぬことである。私はたまらなくこの瞬間が好きだ。 アタックにはやや遅い6時30分、最終キャンプを出る。私と山口、岡林と田村でザイルを組む。大きなクレバスを迂回しながら南西壁に近づく。左の西陵と右の南西稜に挟まれた三角形の南西壁は、頂上にヌンの山頂を抱く雪壁を形成している。上部はかなり急で西稜側から雪庇が張り出しているので、南西壁の直登は困難を伴うが、積極的にこの壁を利用し高度を稼げば、岩の露出した西陵にルートを採るより、早いかもしれない。 そう私は判断し南西壁にラッセルを切り始めた。今までの海外登山ではトップに立ちルートを拓いてきたが、腰痛とアキレス腱痛に悩まされ今回は、後方で荷上げとルート工作をしてきた。トップに立ってきた山口・岡林も疲れが出ている。 |
 |
Page2 |
|---|
|
今日ぐらいは私がトップでラッセルを切らねばなるまいと決意し出発したが、高々15㎝の深さのラッセルが腰痛を刺激するのである。いたしかたなく1時間程でトップを山口に代わってもらう。 南西稜の中央寄りにラッセルを切り続ける。岡林・田村のザイルペアーが遅れがちになる。田村の調子が悪いようである。時々立ち止まっては岡林が田村に声をかけている。壁の傾斜が強くなり、堅い氷の上に新雪を乗せた南西壁に雪崩の恐れが出てきた。 |
南西稜へのトラバースを見ていると、雪崩が発生する限界点に、傾斜も雪の状態も達していると感じる。一刻も猶予できない。雪崩の危険地帯からいかに早く脱出するか。 南西稜の岩稜に固定ロープを発見する。 もたもたしていると雪崩に巻き込まれ南西壁直下のクレバスに吸い込まれてしまう。岡林の下降を待たず、山口に西稜へのトラバースを指示する。西稜と南西稜の間の短い雪 |
壁が、ほとんど垂壁を成している。雪崩を誘発しないようにラッセルを切る。西陵稜に飛び出すと白い雪稜が、緩やかに延び上がっていた。 信じ難い近さにピラミダルな山頂があった。この瞬間、私は全員登頂を確信した。 岡林・田村のザイルペアに声をかけ、標高7千mの碧空に浮かぶ純白の雪稜を辿る。両側がスッパリ切れ落ちた細い1本の稜が、鮮やかに上昇する。風が怒号し白い稜の雪を叩き落とし、ラオヘンを上げる。山頂に至るあまりにも美しい雪稜を前にして、思わず私は叫ぶ。 |
 |
Page3 |
|---|
|
北西稜と西稜の二本の白銀のスカイラインに支えられた山頂が光る。今まで数多くの山巓に立ち、その都度新たなる感動を咬みしめてきた。三度に亘る初登頂の瞬間。
|
登高時の短時間が無限に長く感じられ、立ち止まっている休息の一瞬のうちに数時間が経過する魔の時間帯に突入したのだ。あえて深く激しい呼吸を意識的に行う。 美しい雪稜の均衡を破るように北側に向かって水平に柱状岩が突き出ている。雪稜のやや下から羅針盤の針のように突き出た岩は北を示したまま動かない。これを越えると美しい雪稜が突然終わる。南に張り出した雪庇を付けて山頂が目の前にあった。最高点の一歩手前で山口と握手する。 |
「ごくろうさんでした」 12時35分登頂。岡林が10分遅れて、疲労困憊した田村と共に上がってくる。北側のバルカティック氷河源頭の谷にガスが渦巻き、速い速度で西へ流れる。ガスの切れ間に氷河のセラックが見え隠れし、ガスの上には7077mの岩峰、クン峰が聳える。 |
 |
Page4 |
|---|
|
下降の不安はあるものの山頂に立ってみると予想外に、あっけ無く終わってしまったという実感に捕らわれる。テープレコーダーをザックから出し登頂の瞬間を録音する。 怒号する激しい風に声が千切られる。それにしてもおかしい。ヌンの標高がすぐ出てこない上に、7135mを7315mと間違えてしまった。低酸素の障害だろう。 「岡林です。初めての7千m峰、ついにやりました。頂上に着いた瞬間思わず涙ぐんでしまいました」
|
半分以上は風に吹き飛ばされてしまい、何を言っているのかよく聴き取れない。 八ミリの映画製作を担当する私としては、八ミリも回さねばならないし、音も取らねばならぬし、スチール写真も撮らねばならない。日本、インド両国の国旗と隊旗を出し、ピッケルに結び付け撮影を開始する。 テルモスの紅茶を飲む。コップに落ちる前に紅茶が水平に飛ぶ。強風に打ち勝ってコップに入った液体を飲み干し、時計を見ると山頂に着いてから40分が経過している。 |
私がオーバーズボンをはかないのは、耐寒訓練の意味も少しはあるが、むしろ登高時のスピードアップと発汗による体力消耗を防ぐためである。速く登り速く下降する。 高峰登山ではこれが一番安全である。速く登るためにはオーバーズボンは邪魔である。それに速く登ると発汗度が高まり、オーバーズボンをはいていると更に発汗の可能性が高くなる。 高所に於ける発汗が、どれ程の体力消耗と寒気に対する危険性を孕んでいるかは言うまでもない。しかし稜上に出て、激しい風に身を晒された時には、体感温度は一挙に20℃以上も下がることがあり、オーバーズボン無しでは極めて危険な状態になる。 急激な体温低下は、筋肉の麻痺を起こし行動不能に陥らせる。更に思考力の低下、凍傷の促進を生ずる。 着脱可能なオーバーズボンを用意し、情況に応じて着脱するのが一番良いのだが、現在使用しているゴアテックスのズボンは、裾の開閉度がやや小さく、二重靴をはいたままでは、着脱できないのである。ザックの中のオーバーズボンを恨みながら寒気に耐える。 |
 |
Page5 |
|---|
|
坂原・山口・岡林・田村の順で下り始める。長く感じられた西稜も下ってみるとわずかである。西稜から南西壁に移る急な雪壁で、氷上の雪がスライドし足を取られ転倒する。 左へ左へルートを取り、南西稜の位置を確認して高度計と照らし合わせ、現在位置を割り出そうと試みる。しかし左へのトラバースを始めると、雪壁の部分が雪崩そうになり、結局一直線に真下に下る。 |
広いプラトー上の小さなテント、キャンプ3をこのホワイトアウトの中で、果たして見つけることが出来るか。ルートファインディングに失敗し、ビヴァークを余儀なくされる場合もチラチラ考えつつ下り続ける。 「これで助かった」 下降中、抱き続けていた不安が一度に消えた。あとはラッセルトレールの導くまま下れば、キャンプ3に出るはずである。 |
安堵と共に急に疲労が重く伸し掛かり、腰痛が始まる。ザイルが重い。肉体が重い。全身の筋肉内に乳酸がぎっしり詰まった感じになり、動きが鈍くなる。 結論から言うと、私の場合5時間で脱水症状を起こし手足の痺れが始まり、目の前がぐるぐる回り出す。下降は出来るが登高は不可能になる。現在の私の条件、身体171㎝体重60㎏で余分な脂肪を蓄えていない状態では5時間が限度のようである。 (身体に脂肪を付けている者程この限界時間は、もっと延長されるが逆に余分な脂肪が負荷を増大させるので、運動そのものが続けられない。激しい運動をする者にとって、やはり余分な脂肪は禁物である)症状の解消は極めて容易である。 |
 |
Page6 |
|---|
|
運動を停止するか、水分とカロリーを補給すれば、2、3分で嘘のように症状が消え回復する。カロリーと水分を補給すれば、3分後には再び登り続ける事ができる。 |
低酸素条件が加わっているため症状は異なるが、まだ充分動ける。下降開始後、3時間半が経過。やがて白いガスの彼方に、仄かにキャンプ3が現れた。 ヌン峰の雪を浮かべたウィスキーを飲み干す。重い荷と長い距離の下降で、疲労困憊した肉体に心地良くウィスキーが染み透る。肉体と精神の激しい酷使ほどウィスキーの味を高めるものはない。 |
この一瞬のみ、私はヌンと呼応し共感する。50年後、私はもうこの世に存在しない。ヌンは何も変わらず、このままの姿で、この瞬間のように50年も存在しているだろう。 |
5 絵画交換展
 |
Page1 |
|---|
|
子供達の国際絵画交換展は今回で8回目になる。アフガニスタン、パキスタン(チトラル)、ペルー、中国(カシュガル)、タンザニア、パキスタン(ラワルピンディ)、ソ連(グルジア)、そして今回のインド。 相手国で絵画展を開催出来たのは、パキスタン、ペルー、中国、ソ連、インドである。各国の文化に対する方針や、在日本大使館の協力の程度により絵画展が開けるかどうかが決まる。 |
関係諸機関に何度もお願いしたにもかかわらず、絵画の持ち帰りが出来なかったのはソ連である。他の国もスムーズに応じてくれたくれたわけでなく、登山隊の帰国後、大使館を通して絵画を送ってくれた例もある。 絵画展は登山隊が相手国に到着した時から登山終了の8月末まで開かれる。絵画展を開く学校を訪問し、日本の子供達の絵を展示し100人分の絵の具やクレヨン、パレット、画用紙等を贈呈する。 |
物質の豊饒がもたらす貧困の中で生活する日本の子供達と、物質の欠如した辺境の地で自然と共に生活する子供達は、現代文明の両極端に位置する貧困の犠牲者である。
今回インドから持ち帰った作品は327点で、内訳は絵画303点、ローケツ染め6点、焼物18点である。そのうちの16点を白黒の写真にして次頁に収録した。 |
 |
Page2 |
|---|
|
破壊の神シバも子供達は好んで描く。インドでは飢えた人々が路上で寝転んでいる姿をよく見かける。空の食器を前に泣く子供、為す術の無い父親。これ等を冷静に描きながら同時に、「未来を支えることを誓う」といった類のポスターを描く。 |
6 ポーター変じて強盗に
IMFへの提訴
 |
Page1 |
|---|
|
IMFへの提訴 ヒマラヤに於ける、ポータートラブルは大なり小なり遠征につきものであるが、今回のトラブルは、強盗に近い悪質なものであり、黙認すると、今後インドヒマラヤを目指す世界の登山隊の被害も考えられるので、事実を公表し、IMFにしかるべき処置をお願いするものである。 (1) 場所・インドヒマラヤカシミール地方 ヌン峰(7135m)山麓タンゴールの村 (2) 期日・1985年8月19日 午前9時~10時 (3) 被害隊名・インドヒマラヤ川崎市教員登山隊 1985年 隊長 坂原忠清(40歳) 隊員 岡林良一(33歳) 山口 均(28歳) 田村大作(23歳) (4) L.O.・Capt.GURVINDER SINGH(27歳) (5) 加害ポーター・ポーター頭 (6) 荷下げルートーヌン峰 センティック氷河BC(4200m)よりタンゴール村(3400m)まで標高差800m (7) 事故の概要 一日一人40₨で契約したポーター達が、荷運びの途中で突然一人200₨を前払いせよと言い出す。拒否すると、「払わないなら、お前達を殺す」と脅迫する。結局契約の4倍近い一人150₨を強奪される。 (8) 事件発生までの経緯 8月18日ABC(4800m)より、BC(4200m)まで7人のポーターを使い荷をおろす。一人350₨(前払い分50Rs)で契約し荷下し後BCで契約通り350₨を支払う。 |
支払後明日19日のポーターの給料について話し合う。カルギルのJK政府で発行しているレギュレーションでは、ポーターの一日の給料は35₨となっている。 翌8月19日朝7時、我々の余った食糧、装備等をねらって契約より多い20人程のポーターが集まる。梱包の結果ポーター10人で足りることがわかったので、LOを通して2人分の解雇を申し入れる。キャンセル料としてザイル50mを要求されたので2人に50mのザイルを渡す。 「タンゴールに着くまでだめだ。もうすぐじゃないか。」 「1人200₨だ。」 LOはすました顔で言う。昨日LOを通して一人40₨と契約したはずである。給料の値上げやストライキなら、どんなに多くても契約の2倍を超えることはない。何かの間違いだろうと思い、LOに確認すると「確かに一人一日200₨だ」と言う。 |
のやりとりが続くが、やがて激したポーターは、「もし、支払わなければ、お前達を殺す」と言い始めた。 「200₨を要求する理由は何だ」 「今日は麦刈りや収草刈りがあるのでとても忙しいから特別料金だ」 「そんなのは理由にならない。もし本当にそうなら、昨日の契約の時、申し出るべきで、きょうになって一方的に突然200₨を要求するのはおかしい、約束の40₨を守るべきである。」 登り荷上げのキャラバンでポーター頭だったタケが今度のポーター頭、ハッセンに「早く金を払え。お前の責任だ。払えないなら時計をよこせ」と言ってハッセンにとびかかり腕から時計をはずす。 「一人に200₨も払える程、たくさんのルピーを持ってない。」 「それなら靴とクライミングコートと寝袋を置いていけ、置いていけば150₨でよい」 殺すと脅した後のセリフが追いはぎ宣言である。話し合いの出来る状態ではない。岡林が一歩ゆずって、「靴もコートも今使っているものしかないので、やるわけにいかないが靴一人分なら自分のをやっても良い」と言っても「だめだ、全員分よこせ」「早くせよ、そうしないと、荷を全部谷に放り投げるぞ」 すぐ目の下はスル河支流の激しい流れが渦をまいている。もしデモンストレーションで1個でも投げ込まれたら回収は不可能である。 |
 |
Page2 |
|---|
|
ポーターが要求を始めてから1時間が経過し、ポーター達が殺気立ってきたこともあり、金を払うかはっきりと対決姿勢を打ち出すか結論を迫られる。 「金は払う。しかし多額のルピーは持っていない。一人70₨なら支払える。装備は渡さない。これ以上の譲歩はできない」 更に20分を要し、すったもんだした結果一人150₨11人分を支払うことで話が決まる。隊のルピーでは足りず、隊員個人のルピーを集め、やっと支払い、キャラバンを再開する。 金を手にしたポーターは、ここからタンゴールまで走る。わずか10分で着いてしまう。タンゴールに着くと、それまで黙っていたLOは、ポーター頭と連れそって村に入り、しばらくしてから、彼等の織った絨毯を手にして帰ってきた。「彼等から買ったのだ」と言う。 (9) 事件の推察 第一に我々は事件の首謀者としてLOを疑った。IMFレギュレーションには「LOはポーターの雇用や登山隊が病気や事故に遭遇した場合等には隊を助成する」と明確にうたわれている。 |
○
物品の要求・・・「LOには隊員と同様な装備を与える。ただしピッケル、アイゼン、ユマール寝袋のような装備は遠征終了後、隊に返還される」とレギュレーションには明記されているが、これを返却しないどころか、この他にテント、背負子を要求する。 ○ その他・・・下山のための梱包作業中、ポーターに食糧や装備を勝手にやってしまう等、多くの問題があり、常に隊の行動をみだす原因を作っていた。 これらの行為は直接ポーターの事件と結びつくものではないのだが、一日遅れで下山したフランス隊は一人45₨払っただけで何のトラブルもなかったという。 |
後日LOに200₨を要求した時、どうして黙っていたのかと聞いたら、「3年前、ザンスカールでポーターに口出ししたLOが竹の棒で殴られたことがあったからだ。」と答えた。 スリナガールで観光局のアシュラにこの事件を訴えるべく、LOを伴わずに出かけたが、不在で会えず、IMFではLOと共にデブリーフィングを行ったので、事件の概要のみを伝えるだけにとどめた。当初は第2にポーター達だけの共同謀議も考えたのだが、フランス隊の話を聞いてから、その可能性は薄いと考えるようになった。 |
7 えぴろーぐ
 |
Page1 |
|---|
|
玄奘三蔵はスリナガールで2年間を過ごした。 ヒマラヤの水を集めた美しい森と湖の地スリナガールで、玄奘は法師サンガヤサスに師事し、仏教を深めた。 玄奘が称えたように、確かにスリナガールは光と水と森に満ち溢れた美しい町であった。 ヌン山巓から私にもたらされたものが、こんな結果になるとは予想もしていなかったことである。 登頂をはたしたヌン峰そのものへの思慕が色褪せたわけではない。 登頂の瞬間を想うと今でも自己の存在感が鮮明になる。 しかしインド亜大陸の巨大な隆起は、思惟の波紋を十重二十重に投げかけ、山巓そのものへの思いを忘れさせる程、激しく私に迫った。 スリナガールの至る処で陽炎のごとく立ち登る思惟の波紋は、ヌンの悠久なる断層で再生され、私の内部で「劫の彼方へ」と結実した。 眩惑に満ちた鮮やかなスリナガールの夏は終わったのだろうか。それとも始まったのであろうか。 |
Index
Next