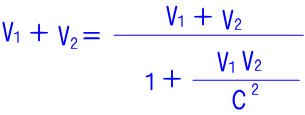|
風雪の西壁
BC建設後15日目、午後は毎日、雨か雪という悪天の中でルートを拓き、3名で第一次アタック隊を行った。
山口は凍傷と高山病で、頂上台座に取り付く前にリタイヤ―、そのままC3へ向かい行方不明。他の2名はバッインシャルテ手前の北肩へ出るルンゼを間違え、登攀不能になり凍傷を負いつつ撤退。第一次攻撃は失敗。
中島は鷲の巣岩壁で墜落後カンバックし、再びC2へ向かうが力尽き、氷壁の途中に荷をデポしBCへ下る。
更に大谷は鷲の巣岩壁上部のC2から、キャンスホッファー氷原のC3への荷上げで疲労困憊し、よれよれになって夜、かろうじてC3に着く。大谷もC3より上のキャンプではもう使い物にならない。
これで7名中の3名が潰れた。残るは4名。1名又1名と倒れていく隊員を目の前にして、第二次アタックを行うべく、私は田村と共に前進を続けた。若しかすると私は、ドイツ隊の隊長メルクルと同じ途を、突き進んでいるのかも知れない。
あの日のように今、暴風雪に襲われたら、たぶん私もメルクルと同じくビヴァークしているであろう。山口を始めとし、疲労の激しい隊員から次々と高所キャンプで息絶えるであろう。
だが暴風雪がやってくるまでに3時間あれば、死の高所キャンプからの脱出は不可能ではない。総てを捨て全力を尽して、スピーディーにアップザイレンを行えば、表層雪崩に襲撃される前に、急峻な西壁から逃れることは出来るだろう。
暴風雪による撤退の判断を、一瞬誤れば、いつでも私はメルクルの悲劇を繰り返すことになる。そしてその正確な判断は、偶然に支配される可能性が高いとなると、もう既に私はメルクルなのかも知れない。
|
|
キンスホッファー氷原へ出る岩と氷のミックスした岩稜は早々とガスに包まれ風雪がハミングを始めた。
入山以来1日として午後まで晴れた日はない。朝方の僅かな晴れ間を利用して行動を開始するが、どうしても雪の始まる時間帯を避けることは出来ない。
しかし今日は特にひどい。まだ午前10時前だというのに、もう風雪がハミングを始めたのだ。ガスに包まれ、雪が舞い始めると急激に温度が下がる。頬が凍り、髭に雪が付き氷柱になる。眉や睫も凍り、瞬きすると互いにくっつき合い視界が閉ざされる。
風が雪を吹き上げブリザードになると、天地の区別が曖昧になり、雪面と空間がつかなくなる。風雪の白と雪壁の白とが作るホワイトアウトの視界は零に近い。形と色、距離と時間さえも失せた奇妙な空間は、視界零でありながら、無限の広がりを持つ。
どんなに必死に登り続けようが、決して抜け出すことが出来ない絶望感を突きつけ、我々をパニックに陥れる。
確実な方向を示す唯一の固定ザイルは、昨夜の雪に埋まり、更に今日の新雪に覆われ姿を見せない。今日も1日中ザイルを掘り出しながら、前進せねばならない。
岩稜から雪稜に変わり、キンスホッファー氷原直下の雪壁に出ると、間断無く表層雪崩が流れ始めた。雪稜が急峻なため、降った雪は即雪崩となって落下する。
流れ続ける塵雪崩の落下距離を考えると、ぞっとする。このホワイトアウトの上部は、標高差700mの広大な氷雪壁が立ちはだかり、我々の頭上を圧しているのだ。
氷雪壁に落ちた雪が風によって舞い上げられず、そのまま積り始めたら、表層雪崩は強大な威力を発揮し、700mを一気に落下し、一瞬にして我々を吹き飛ばすであろう。
|
|
塵雪崩が流れ続けること、それが我々の安全を保障する、1つの目安になる。しかしその塵雪崩が、次の瞬間に突然規模を変え、雪の津波となって我々を襲う可能性も又充分にある。
正確な予測は誰にも出来ない。
こんな危険な状態の雪壁では、行動しないことが一番安全なのだ。だが我々は一定のリスクと困難を甘受し、敢えてナンガへやってきた。
一番安全な状態を求めるならばヒマラヤへなんぞやって来るはずがない。撤退には何の意味もないのだ。私の理性は表層雪崩の真只中で「GO」のサインを出し続ける。
初めてではない。何度か同じ状況下で私は登り続けてきた。そして生きて還ってきた。決して私の理性が狂っているわけではないのだ。私の理性は最良の結論を下し、「出発せよ」と熱く囁く。
かつて凍傷にやられた手の指の痛みが酷くなる。両手の小指全体と他の指の第二関節から上が、切断寸前の凍傷にかかり、以後この部分が特に寒さに弱くなっている。又痛み出したのだ。
標高はまだ6600m程だが、手袋を二重にせねばならない。
「田村、悪いがザックの天蓋からオーバーミトンを出してくれ」
固定ザイルに確保を取り、天蓋のチャックを明け、ミトンを取り出さねばならない。この状況下では大変面倒な作業を田村がやってくれる。
ミトンを出した瞬間、9000mまで計測出来る高度計が、天蓋から落ちる。雪面に落下すると同時、右手のストックで反射的に押さえるが、急峻面なので、すぐ滑り出す。
|

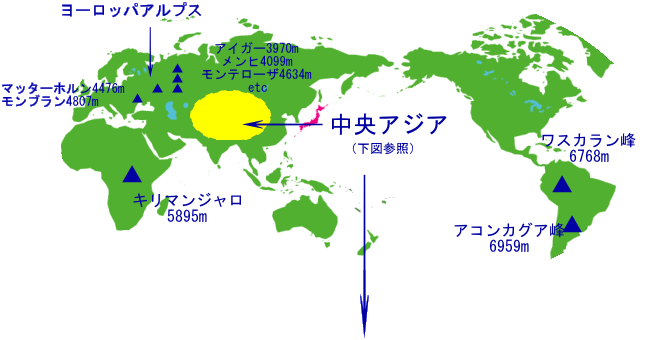
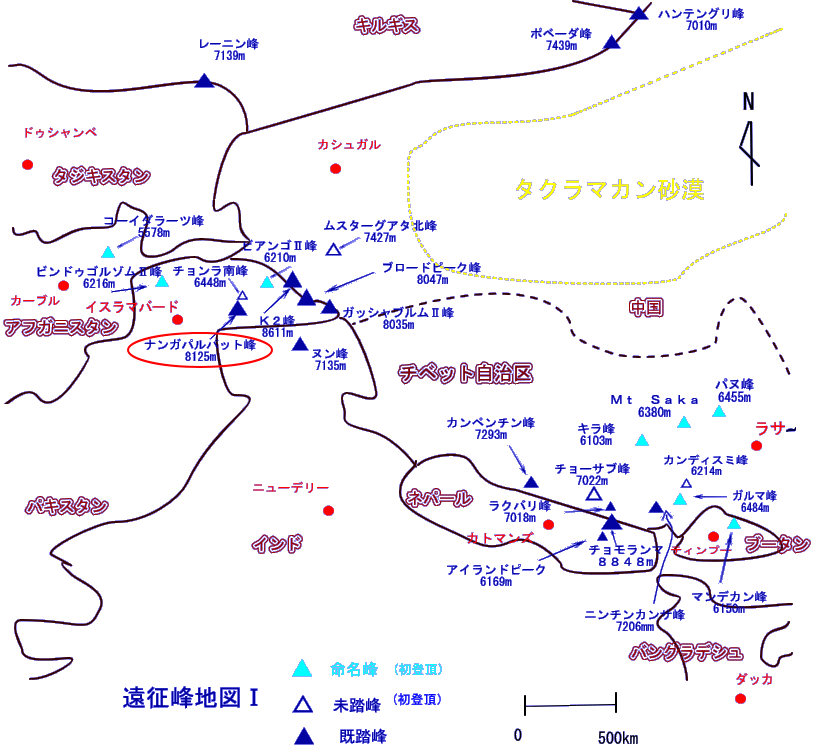

 BCから仰ぎ見る西壁
BCから仰ぎ見る西壁