
最後の白馬主稜・・・白馬岳から不帰へ
ナンガ・パルバットに消えた中島修
記録: 坂原忠清
|
・
凍結した彼の肉体は神々の座で 数千年の時を超えるのだ。
|

| Contents | |||
| 《A》 | 小窓尾根・・・風雪の剣岳 | 12月~1月 | 1986年~87年 |
| 《B》 | 鹿島槍北壁&東尾根・・・冬の鹿島槍集中 | 12月~1月 | 1990年~91年 |
| 《C》 | 最後の白馬主稜・・・ナンガ・パルバットに消えた中島修 | 3月 | 1990年 |
| 《D》 | 奥穂南壁の奇跡・・・明神岳東稜 | 3月 | 1991年 |
| 《E》 | ナンガパルバット合宿・・・風雪の槍ケ岳北鎌尾根 | 3月 | 1989年 |
![]()
 |
Page1 | 初出:岳人523号、524号 |
|---|
|
山巓より緩かに広がる白いレース、冬の白馬主稜。 ヒマラヤを夢みる新人2名の遠征隊員選考を兼ねて、3月の白馬主稜に入った。それは3度目のナンガ・パルバット遠征計画の最終合宿であると同時に、私にとっては追憶の山旅でもあり中島にとっては終焉の山行となった。 二人の新人 3月27日(火)曇後風雪 急な冷え込みでパリンパリンに凍りついた主稜末端の雪壁を登り始めると田口が叫んだ。 「やっぱりだめです。登れません」 183cm、75㎏、24歳。小柄な隊員の多い我等がチームの中では巨漢である新人の田口がギブアップした。 主稜に入ってからでは、新人を一人で下山させる訳にはいかない。今なら可能である。私は田口の下山に同意。 「よし。田口の荷は主食だったな。ラーメンα米を出せ。3人で分けて持っていこう」 私と中島と成田の3人の分担を決めると中島が田口に話しかける。「あのー、ウィスキーを2本持ってましたよね。テルモスに入れていくから下さい」 これには私も亜然とした。
|
昨夜もビール4ℓワイン1本、ウィスキーをたら腹飲み、まだ各自のザックには1ℓ以上のウィスキーが残っている。ウィスキーは充分にあるのだ。それより4人の荷を3人で担ぐことになった為更に重くなったザックを気にすべきなのである。 特に中島の荷は、テント、コッフェル、ガソリンと重い物ばかりで、いつものように30kgは越えている。それに食料を加えるだけでなく、ウィスキーまで荷上げしようと言うのだ。 それを聴いて新人の成田は『ウィスキーより田口の持っているリンゴのほうが良いな』と思ったと後日述べた。確かに正統な山岳会ならそう判断するに違いない。だが我等がスビダーニエ同人は正統のセの字も無い集団である。これで良いのだ。 急な雪面でザックを開け、食料を取り出す。キャベツが一巻、田口の手をすり抜けて、ハイスピードで雪壁を落ちる。 昨日、今日の動きから判断すると田口の技術、体力では、キャベツと同じ運命を辿ることは、ほぼまちがいない。 もう1人の新人成田がトップに出て、凍りついた急斜面にアイゼンの爪を立て稜上に向かう。高校時代、陸上長距離で鍛え、フルマラソンを2時間40分台で走る成田の体力は抜群である。30分程で末端ピークに連なる主稜線に出る。
|
去来するガスの谷間に時々顔を見せた蒼窮は、完全に姿を消し雪混じりの北風が吠え出す。移動高が日本海に入ったはずなのに、おかしい。きっと移動高の速度が遅く、冬型の残滓がウロウロしているのであろう。 6峰のコルでザイルを出しアンザイレンする。細く急な雪稜が10m上方に延び、その上はやや傾斜を落し再び広い雪稜になる。普通の状態であるならアンザイレンの必要はないが、今回はパリパルに凍りついており、ツァッケ2本とピッケルのピック、アイスバイルの先端でバランスを保ちながらの登攀となるので、ザイルを結ぶ。 私がトップに立ち、成田、中島の順にザイルを結び登り始める。ふくらはぎの筋肉が堅くなり、ギンギンと痛む。氷の斜面では足がフラットに置けず、主稜に入ってから重荷に喘ぐ筋肉は緊張を強いられ続けている。 痛んであたりまえなのだ。だがあと数時間耐えれば、筋肉は氷の登攀を思い出すのだ。そしていつもの山行のように快適なリズムを取り戻すであろう。岩稜に新雪の乗った5峰の直登を諦め、後からきた成田に左へのトラバースを指示した。
|
 |
Page2 |
|---|
|
不安定な足場、そしてピッケルを打ち込むことの出来ない岩稜。瞬時に確保する術のない私は、岩角にかけた指に力を入れ、ザイルにかかる急激なショックを、待つしかなかった。一瞬にしてはじき飛ばされ、滑落する3人の映像が浮ぶ。猛烈な加速の始まる寸前に、奇跡的に成田が止まった。 5m程下に細い岳樺の枝が出ており、左手で成田はそれを掴んだのだ。3人を結んでいるザイルがショックを緩和したことは確かであるが、あの細い枝でよくぞ停止したものである。 「足を痛めなかったか。動けそうか」 「大丈夫です。動けます」 このトラバースでの滑落は、予想もしていなかった。登ってきた成田に滑落の原因を問うと、アイゼンを蹴り込んだ足場が崩れたとのことであった。 雪壁登攀の経験の浅い成田にとって、ツァケ2本で身体を支えたり、僅かなステップに全体重をかけるのは、たまらなく不安なのであるしたがってトップの私が残す小さなステップに乗ることが出来ず、自分で何度も蹴り込みステップを大きくしてから体重移動を行う。 確かにステップが大きくなれば安定するが、同時に不利な状況も生む。1つは表面が堅く凍りついたクラスト面をこわし下部の軟雪部を露出してしまうため、足場が崩れやすくなることである。成田の足場が崩れたのは、これが原因である。 もう1つは疲労が累積されることである。当然のことながら1度の蹴り込みより2度の方が疲労は倍加する。数千回の蹴り込みを必要とする長い登攀では、その差は顕著に現れる。
|
凍った急斜面では僅かなミスが即、死につながる。したがって確保が出来ない限りザイルを結ばないのが原則である。 1人の滑落がザイルシャフト全員を落下させてしまうからである。だが私のザイルシャフトはほとんど、ザイルを結んだままコンテニァスで行動することが多い。 ヒマラヤでも日本の冬山でも登攀は常に天候と時間との闘いである。氷壁や山稜に身を晒す時間が長ければ長い程、危険は増大し疲労は蓄積される。 安全性を高めるにはスピーディーな行動により登攀時間を短縮することである。コンテ登攀はスピーディーであるが、リーダーの正確な判断が要求される。ルートの難易度とザイルシャフト1人1人の技術を適確に把握し、コンテかスタッカット登攀かを決定し、スピーディーに登らねばならない。 コンテ登攀が多くなればなる程、時間は短縮されるが確保がないため、ザイルシャフト全体の滑落の危険性は、増大する。つまりザイルシャフト各自の技術が、ルートの難易度に勝っていればコンテ登攀は、積極的に安全性を高めることになるのである。 新人成田を2日間観察して、経験は浅いものの基本的な技術、体力に不安は感じなかった。3月の主稜は成田にとってコンテ可能なルートであると私は判断したのである。 滑落後の成田は更に慎重になり、急な雪壁ではステップ作りのための蹴り込みの回数が増え、登攀スピードが落ちラストの中島をイライラさせたが、安定感のある登り方で私の判断に狂いはなかった。
|
5峰、4峰を超え午後になると風雪が強まり、体感温度が低下し始めた。マイナス16度、風速20m。オーバーミトンの中で指先がしびれ痛い。 緩やかに起伏する雪稜を3峰に向かって中島がラッセルを続ける。重荷を背負って3時間もトップを務めているのに、ラッセルを交代しようとは言わない。 中島も合宿毎に強くなっていく。彼の胸には4ヵ月後に迫ったナンガ・パルバット遠征でのサミッターの夢が去来しているのだ。 『真に強いものだけがナンガの山頂に立てる』ということを3年前の失敗で、身にしみて中島は実感したはずである。中島を除いて全員がナンガ西壁最終キャンプに入りアタックをかけたのに、若い25歳の中島だけがC2までしか到達出来なかったのである。 成田の足がもつれてきた。スピードが落ちトップのラッセルを追っていくのが精一杯である。やがてトップとの差がじりじりと広がり始めた。 これ以上無理をさせると明日動けなくなる可能性がある。3ヶ月前の冬合宿、豪雪の天狗尾根でも風雪の中9時間行動した後、新人の小川は食欲を失いテントの中で1人ふるえていた。 新人の持っている能力の限界値を僅かに超えたところを見極め、行動を打ち切らないと、再起不能になってしまう。時刻は1時30分、トップとの差を調整するため休憩をとり、行動食をとる。
|
 |
Page3 |
|---|
|
「今日は2時で行動を打切ろう」 鋭利な雪稜に立ち風雪に叩かれドラヤキを頬張りながら2人に告げる。吹雪のヴェールを通して左側に時々尾根が見え隠れする。すぐ目の前に忽然と現れてはホワイトアウトの中に消える。三合尾根である。 頂上が近いことは確かであるが、この次のキャンプサイトは2峰を越えないと無い。この条件下で2峰の上まで登り続けるのは苦しい。仮に登ったとしても2峰上部は頂上稜線の大雪庇の真下にあり、そこで一夜を過ごすのは精神衛生上良くない。 この細い雪稜を切り崩してテントを張るしかないであろう。キャンプサイトを求めて再び雪稜にラッセルを開始する。200m程進むと雪稜が白馬沢に僅かに張り出している。雪庇なのか尾根なのか判断出来ない。しかしこの場所をのがすと最早2峰上部まで平坦部は無い。 雪稜から身を乗り出して雪庇か否かを確かめるがわからない。たとえ雪庇であったとしても、マイナス16度の堅く凍りついた今日のコンディションから判断して、まず崩壊することはないであろう。 私の直感ではまず安全である。幕営を決断し雪稜の雪を削る。スコップでブロックを切り風上の白馬沢側へ積む。 テントに入って日本酒で乾杯。一升の酒があっという間になくなりウィスキーを飲む。 大いに飲み語り健やかに眠る。
|
何とも不思議である。45歳を超えた肉体は下界の日常界ではそれなりの老化現象が始まっているのに、日常生活よりはるかに苛酷な雪と氷の世界では、精神も肉体も20年も時を溯ってしまうのである。 下界で飲む酒なんぞはうまくない。少し飲むとうんざりしてしまう。当然飲みすぎると翌日は疲労が残る。眠りは浅く常に肉体が重い。10数年続けている朝のジョギングも最近は気分壮快どころか、筋肉内の乳酸が蓄積されて不快である。 この状態で重荷を担いで雪と氷の世界に入ったら1時間ももたず、のびてしまうに違いないと確信したのが2年前である。以来今度の合宿こそ現役最後と覚悟を決めザイルのトップを努めてきた。 だが何とも不思議である。山に入ると酒はうまいし、いくらでも飲める。その上眠りは深く疲労は心地良く、全身の諸機能を活発にする。肉体は軽くなり苦痛を積極的に受け入れようとする。20代の輝ける肉体と精神が復活するのである。大いに飲んだくれてシュラフに潜り込む。 何の夢を見ていたのだろう。兎のように身を丸めて雪の中で眠っていた私は尿意を覚えテントから這い出し雪稜に立った。 空間の総てが星の海であった。地には生命の灯す星々の光が満ち、天空には数億年の彼方から旅してきた宇宙のパルスが煌き、確かにそれらは同一の星々であった。 柔らかい夜のシルエットをまとった幾つもの雪稜が緩やかに下降し、安曇野に落ちる。静謐と闇を湛える漆黒の湖面であったかっての夜の安曇野は、今は星の海であった。
|
あの1つ1つの灯が生命の営みを告げているのだ。やがて地の星々は遙かな時間を突き抜けて、いつの日か天空の星々に至であろう。 青い宇宙へ 3月27日(火)晴マイナス19度 私の直感は今度も運良くあたった。雪庇と共にテントごと白馬沢に落ちることはなかった。風はまだかなり残っているが雲は去り、青空が広がっている。 晴れさえすれば3月の北アルプスは、こよなく美しく光る。ヒマラヤのような風格さえ見せる。朝の光をいっぱいに浴び、優美な雪稜が頂上直下の雪壁に連なる。雪壁部は大きな雪庇が覆いかぶさり、黒い影を作っている。2峰の正面を突破しようと雪壁に取り付くが、5mも進まぬうち前進不可能となる。 急峻な雪壁の下はブッシュとスラブで極めて不安定。ラッセルしても雪は固まらず、雪壁全体が雪崩そうである。腰まで沈み込む。急傾斜のため顔が雪面にくっつきそうになり、身動きができない。斜度を緩めるため右へトラバースを試みるが進めない。無理してトラバースすれば、落ちるか雪崩れるかどちらかである。 「だめだ。これ以上進めない。右のルンゼから2峰の上に出るしかないな。ゆっくり降りるから、しっかりジッヘルしていてくれ」 ルンゼへのトラバースは新雪の雪面を切るので雪崩れるかと思ったが、大丈夫であった。15mトラバースし、そのまま2峰の稜上へラッセルする。ルンゼは何重にもデブリが重なり、頻繁に雪崩れていることを示している。
|
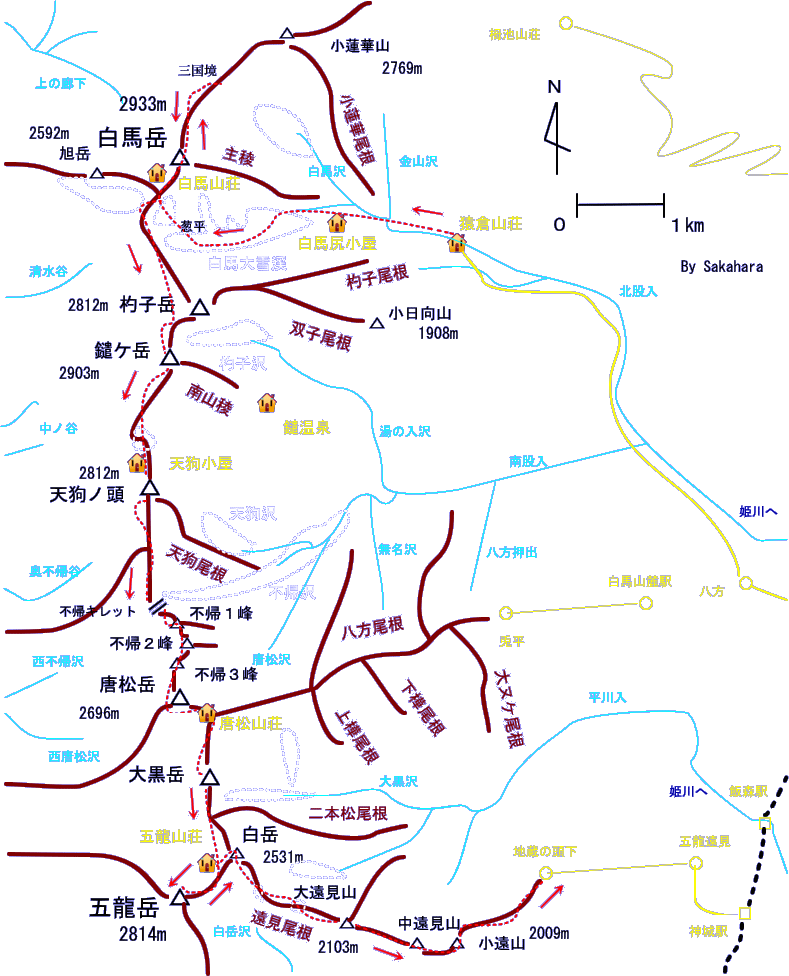 |
 |
Page4 |
|---|
|
雪稜に上ると朝の光が、右ルンゼに私と中島の影を描く。ザイルに結ばれた2人の登攀者が影絵となって、雪のスクリーンに浮ぶ。 「中島、写真撮っておけよ。良いのが撮れるぞ」 この雪稜を超えると頂上直下の雪壁に出る。雪壁のすぐ上に白馬の山頂があるとは、とても考えられない。そこが白馬主稜の面白いところである。北アルプスの数ある積雪期ルートの中でも雪庇を乗り越えた瞬間、頂上に飛び出る豪快なルートは白馬主稜のみと言っても良い。 この上部の岩は昭和6年3月31日に田中伸三が、積雪期初登攀の記念にハーケンを打ち手ぬぐいを巻きつけたところである。60年も昔のことであるが、ひょっとしてハーケンが残っているかも知れないと思い探してみるが、それらしき物はなかった。 雪庇直下までザイルを延ばすと身体は反り返り不安定になる。まず左のステップを大きく切り、アイスバイルをデッドマンにして雪壁にぶち込みジッヘルをとる。ピッケルバンドの長さを調整し、右手首にバンドを固定する。準備完了。ジッヘルしている成田にコールする。
|
「これから雪庇を叩き潰すぞ。雪庇が崩れて一緒に落下するかも知れない。ジッヘル頼むぞ」 右手をいっぱいに延ばすがピッケルは雪庇の端まで届かない。雪庇の根元に穴を明けることにする。ピッケルを振りおろす度に、雪と氷のシャワーが頭に降りかかり首筋に入る。 天蓋に入れてあるマフラーを思い出す。雪壁登攀に入る前にマフラーをすべきだったと後悔するが、この態勢ではどうしようもない。濡れるにまかせピッケルを振り続ける。新しいシモンのピッケルはブレードが小さいので効率は悪いが、軽いので振り易い。 新しいピッケルは1月の鹿島槍天狗尾根で筆おろしをし、3月の尊武、谷川岳で使い今回の白馬主稜とまだ3回目であるが、既にシャフト下部は傷だらけである。前のピッケルと同じように折れるのも時間の問題であろう。 右腕の筋肉がギンギンと痛む。雪庇は予想外に堅い。左手にピッケルを持ち変えたいが左手をアイスバイルの支点から離すわけにはいかない。落ちてしまう。しばらく右腕を下にさげ休息する。
|
雪庇は50cm程抉れた。あとはこのまま穴の中央部を攻め、シャフトで突き破るしかない。休息後ピッケルを持ちかえ、スピッツェを突き刺す。数10回繰り返すと、ピッケルの抵抗が突然消えた。ピッケルを引き抜くと直径数センチの小さな青空が、雪庇の影の中に浮いた。 それは奇妙な青い空間であった。無限の蒼穹が大きな雪庇の影の中で、小さな点を記しているのだ。壮大な宇宙が小さな雪塊に捕らわれた光景であり、マクロとミクロの世界が反転した瞬間である。私はその小さな無限の宇宙を放心したように、しばし見つめた。 ブータン遠征で遭遇した密教宇宙のミクロとマクロの位相変換が甦る。ヨーガによって到達した密教徒達の宇宙観は、現在の最先端の宇宙論と余りにも酷似している。凍りついた雪の結晶の中に浮かぶ、小さな青い宇宙は真理そのものなのだ。瞬時の放心から覚め、私は青い宇宙を拡大する。 「オーイ、穴があいたぞ。頂上だ」 ジッヘルしている2人にコールする。アイスバイルを引き抜き、ピッケルとバイル両方を振るいながら、青い宇宙に飛び込む。雪庇の上に首が出る。左前方15m程の所に山頂があった。拡大された青い宇宙の彼方にはピラミダルな剣岳が大きく聳えていた。 雪庇から出ると平坦な山頂が広がる。垂直の緊張から急に解放された肉体が、僅かな緊張感を残しながら最後の山稜を歩む。
|
 |
Page5 |
|---|
| 3月27日午前10時50分、北風の吹きすさぶ山頂に3人で立つ。20年前の追憶の山行が又一つ終った。ヒマラヤを夢みる若い仲間を連れて、3月の白馬主稜に来ることはもうないであろう。他にも登っておきたい追憶のルートが、まだたくさんあるのだ。 誰もいない人跡の途絶えた山稜を杓子岳へ向かう。岩と氷だけで構成されたアステロイド(小惑星)の1つに迷い込んだような気がする。いやもっと遠い宇宙の惑星上かも知れない。 こんなふうにして岩と氷は数億年も沈黙を続け、何かを待っているのだ。杓子岳への登りにかかり後を振り返ると、山頂直下の主稜雪壁が鋭い角度で青い宇宙を切り裂いていた。つい先程、あの雪庇にピッケルを振るっていた小さな生命が見えるような気がして、目を凝らす。背景の青い宇宙が、うるうると拡がり雪壁を呑み込み、小さな生命の幻影を掻き消してしまう。 何億年も待ち続け、そして最後に青い大海原が、星々に同じ解答・生命の幻影を与えるのだろうか。杓子岳の氷の斜面をトラバースし、白馬槍とのコルに出て行動食をとる。スルメやハムをかじる。本日の幕営地、天狗山荘まであと僅かである。最早カロリーは必要としない。 うまいウィスキーを飲むためには味覚をシャープに保っておく方が良い。カロリーのある甘い食物は味覚を鈍麻するのだ。テントを張り終え最初に飲むオンザロックの味は絶妙である。その日の行動が厳しければ厳しい程、カロリーの摂取量が少ない程、その絶妙さは深さを増す。 |
アルコールは本来、肉体と精神の激しい酷使後に与えられる神々の聖水なのである。下界で何もせず飲んだくれるなんぞは、正に神々への冒瀆である。 疲労が目立ち始めた新人成田も中島もスピードを落とさず進み、コルから1時間で白馬槍の山頂に立つ。 「さて山頂にふさわしい話をしようじゃないか」 と私が切り出す。 「中島は何を話す」まず中島に問い掛ける。 「天狗山荘の冬期小屋が開いていれば、じっくり飲めますね」 「成田は何を話す」 「下山したら、温泉とビールが欲しいですね」 「そうか、よし俺が山頂にふさわしい話をしよう。成田は充分に持久力がある。ナンガの隊員に加えよう。技術的にはまだ未熟だが鍛え方によっては、遠征まで残りの3ヶ月でレベルアップは可能だ。もちろん成田が解決せねばならぬ問題は技術と体力だけではない。家族、職場、資金、休暇、と問題は山積している。しかし強固な意志があれば途は拓ける。その程度の問題が解決できぬようでは、もともと8000m峰に挑む資格はない」 寡黙の成田の決断は一瞬であり行動は素早かった。その日から2週間後には、ナンガ・パルバット最終計画書に追加隊員として、顔写真とプロフィールが印刷された。 フルマラソンを2時間40分で走る成田は、白馬主稜の次の山行ではトレーニング成果を発揮し、9人目のナンガ隊員になったのである。
|
槍を下り槍温泉への分岐をすぎ、なだらかな雪尾根に出ると天狗山荘の小屋が見えた。小屋を一巡するが冬期小屋は無い。小屋から離れ不帰側の窪地にテントを張る。 「山小屋の間に張った方が風に対して安全じゃないですか」と中島が言う。 「強風が予想される場合にはな。だが今夜はまだ荒れないだろう。それより汚らしい小屋の近くに張るより雪と岩だけの空間に張った方が気分良いだろう」 万一の雷の襲来を恐れ、アイゼン等の金属類をテントから離す。即テントにもぐり込みジョニ黒を飲みだす。今日の高気圧は東に去り、明日は日本海の低気圧が東北に進み下界では雨になるとラジオが告げる。当然山では吹雪であろう。できることなら吹雪になる前に不帰を超えたいものである。 宙に浮く雪壁 3月28日(水)曇マイナス14度 6時出発。天狗の頭よりキレットまで一気に飛ばす。左前方の八方尾根に10数人の人影が浮ぶ。山中に入り4日目にして初めて目にする人間の影である。 高曇りの不透明な大気と雪尾根の境界を登る小さな点は遅々として進まない。不帰沢の広大な雪渓にも登山者が見える。不帰の嶮を超えてしまえば、もう下界なのだ。音楽をジャラジャラ鳴らしたスキーヤーのゲレンデになってしまう。
|
 |
Page6 |
|---|
|
不帰1峰のルートは黒部側にとる。下部でヴェルグラをまとったスラブにぶつかりアンザイレンする。上半部は鎖と鉄梯子がかけられてはいるが、鎖は岩壁に凍りつきほとんど使えない。 核心部2峰の北峰のトラバースは最悪の状態であった。急な雪壁が岩壁から浮き、雪庇状になっているのだ。したがってトラバース中に確実な支点を取ることが出来ない。ピッケルを深く刺し込むことさえ危険である。ピッケルの一突きが雪庇を崩壊させる可能性は充分にある。成田にジッヘルを託し、トラバースを開始する。 「いつ雪壁と共に落下しても不思議ではないからな。急激なショックに耐えられるようジッヘルしてくれ」 雪壁に向かい合いショックをかけぬようアイゼンを蹴り込む。15m程で最初のトラバースを終え、小さなコルに出る。 このコルの上が不帰2峰の台形の北側、北峰である。通常ルートは北峰の東側にあり、鎖か針金があるのだろうが今は巨大な雪庇の一部となってほぼ垂直に唐沢側に落ちている。直接北峰へ突き上げる尾根上の岩稜は、上部がややハングしている。ハーケンは1枚も無い。ルートではないのは明らかである。 意を決して雪壁のトラバースにかかる、アイスバールとピッケルを交互に打ち込み3m進むとピッケルの抵抗がなくなった。引き抜くと下は空洞になっており、垂直の岩壁が見える。発達した雪庇が北峰の東側に垂れ下がってできた雪壁であり、半分以上は空中に浮いているのであろう。 |
これ以上の前進はあまりにも無謀である。即引き返す。ヘルメットをかぶり、小さなナップサックを背負ったクライマーが2人、不帰沢より登って来て我々に追いつた。唐松小屋をBCにして不帰のルートを偵察しているとのことであった。 黒部側の垂壁は絶望的であり、直上する岩稜は上部のオーバーハングがネックである。やはりルートは雪壁のトラバースしかない。ザックをコルに置いて、再度空中に浮いた雪壁に乗る。過度の緊張で胃液が出てきそうになる。 「出たぞ。ザックを吊り上げるからザイルに結んでくれ」 その後ザックを上げ、成田、中島と通過するが雪庇は落ちず危機は回避された。2峰北峰でザイルを解き3峰へ向かう。雪と岩で構成されたピラミダルな3峰は、吹雪いていればルートファインディングに苦しむところである。 |
夏のルートは容易であるが、今は雪と氷に覆われ跡形もない。ルートは右の黒部側リッジを巻くのだが、かなり厳しそうに見える。 予想外に易しい黒部側リッジの中央部を超え急なガリーをトラバースし稜上に出ると、不帰の嶮は終る。あとは唐松のピークまで一息である。唐松岳の山頂は最早下界の臭いが漂っていた。 終章 1988年のレーニン峰、89年1月の穂高集中登山、3月の北鎌尾根、8月のブロードピーク。90年1月の鹿島槍天狗尾根、そして今回の白馬主稜と続いたナンガ・パルバット遠征の為の合宿は終った。 日程の都合で今回は分散合宿となり、他隊は北岳バットレスに入っているはずである。我が白馬隊の新人は1名が脱落し、1名が遠征隊員となったが、バットレスの新人はどうなったであろうか。標高差4600mのナンガ・パルバット南西稜は、あと4ヶ月後に迫まった。3年間に及ぶ長い準備期間は終ったのだ。 だがその4ヵ月後に待っていたのは、ナンガ・パルバット山頂直下での中島の死であった。登頂後の戸高隊員によって滑落死した中島はメルクルシャルテで発見され固定された。 6年間、ほとんどの山行で私とザイルを組んだ中島の死は、私の肉体の一部を切り取るような強烈な痛みを伴った。今年のナンガ・パルバットでは中島とザイルを結ぶチャンスは一度もなかった。 |
 |
Page7 |
|---|
|
したがってこの白馬主稜でのアンザイレンが、中島との最後のザイルシャフトになる。終ってしまった最後の合宿。そして最後の白馬主稜。 酒を担ぎ上げ中島と一緒に、冬の北アルプスを駆け巡ることはもう二度と出来ない。ナンガ・パルバットが存在する限り、8000mの高所で彼の肉体は永遠に眠り続ける。
凍結した彼の肉体は神々の座で 数千年の時を超えるのだ。 |
![]() Index
Index
Next